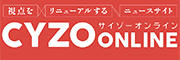前回のドラマではこの手の問題はサラッと流されていましたが、それでも「面白いなぁ」と思ってしまったのは、『助六』が正徳3年(1713年)、矢野弾左衛門からの独立記念に作られた演目だという説があるからです。
『助六』は東銀座の歌舞伎座の正月公演には欠かせない演目ですが、なぜ新年に『助六』を演るのかといえば、歌舞伎役者の地位向上を象徴した実におめでたい演し物だからのようです。俄祭に、さりげなく『助六』のワンシーンを入れ込む脚本家の森下佳子先生にはセンスを感じてしまいました。
さらに前回興味深かったのは、平賀源内(安田顕さん)がエレキテルの修理に成功し、さっそく医療器具として売り出していた場面です。史実でいうと、平賀源内が壊れたエレキテルを入手したのは明和7年(1770年)、長崎でした。当時の日本が正式に門戸を開いていたのはヨーロッパではオランダだけですから、エレキテルもオランダから輸入されたものでしょう。記録によれば、平賀源内は6年かかってこれを修復。模造品も多数作成し、医療器具として、そして見世物として様々な機会に披露し、ボロもうけしたのでした。
静電気がバチッと弾けるのは、「身体の中の悪い気が燃えているんですよ」とか適当なことを言っているな~、と感じるのが我々が現代人だからでしょう。
エレキテルはガラス板と錫箔(すずはく)を擦り合わせて静電気を発生させる仕組みでしたが、18世紀当時のヨーロッパでも、実はエレキテルと同じ原理の静電気発生装置が医療器具として大真面目に使われていたのです。
フランス革命期の政治家として有名なジャン・ポール・マラーの前職は医師で、彼もエレキテルのような機械で患者を感電させて、「治療」していました。それで患者が「治った」と思うだけでも効果があったといえるわけですから不思議です。
当時のパリはウィーンと並ぶ医療の二大拠点でしたが、そのウィーンからパリに引っ越ししてきたフランツ・アントン・メスマーという医師も「動物磁気」なる概念を提案、それを人間の身体に流してバランスを整えることで健康になると訴え、フランスはおろかヨーロッパ中の上流貴族から平民にいたるまで幅広い人気を勝ち取りました。