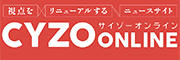『べらぼう』第12回、「俄(にわか)なる『明月余情』」も見どころ満載でした。
『べらぼう』馬面太夫の吉原出禁
前回のコラムで、安永4年(1775年)に吉原で復活した「俄」の時期は春だった云々とお話しましたけれど、ドラマに登場したのはその2年後、安永6年(1777年)の8月に行われた俄祭だったようですね。季節的にいうと、現在の9月半ばくらいでしょうか。
しかし、朋誠堂喜三二が序文を寄稿した『明月余情』は、吉原内の江戸町一丁目の正月行事で始まっています。ここで「秋なのになぜお正月?」と思うのは当然です。当時の吉原の街では正月(1月)、3月、5月、7月、9月にあった、それぞれの「節句」に合わせた祭が年中行事として行われていました。
ところが、この年の吉原俄では、すべての練り物(祭礼行列)を一挙に見せていったらしいのです。ドラマでは若木屋(本宮泰風さん)と大文字屋(伊藤淳史さん)が『ウエスト・サイド・ストーリー』みたいなダンスバトルを繰り広げていましたが、当時の吉原俄のウリも派手な練り物と、素人演芸ショーだったようですね。
禿(かむろ)の少女たちが扮装して、「煙管(きせる)の雨が降るようだ」と市川團十郎ゆかりの『助六(助六由縁江戸桜、すけろくゆかりのえどざくら)』のワンシーンを再現した場面も目を引きました。実際には吉原を訪れた主人公・助六に、並み居る花魁たちが自分が吸っていた煙管を手渡しまくる場面のセリフです。
女性が、好みの男に吸いかけの煙管を手渡すのは好意の証しという当時の決まり事を反映したシーンですが、江戸時代は男女ともに喫煙に対して何のお咎めもなく、高貴な女性もガンガン煙草を吸いましたし、優雅に煙管を使った喫煙は褒め称えられる行為ですらあったのです。
助六役の子役さんの声のハリにはびっくりさせられましたが、興味深いシーンでした。というのも、前回のコラムでは馬面太夫(寛一郎さん)など浄瑠璃の演者も含め、役者など歌舞伎関係者は「被差別民」の扱いだったところを、18世紀初頭に市川團十郎(二代目)が「被差別民」たちのリーダーだった矢野弾左衛門の支配下から独立したとお話しましたよね。