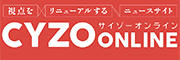文春は、連載コラムなどを充実させ、女性も読める週刊誌路線を確立した。
各社の週刊誌が毎週話題になるため、小学館は、現代の前編集長とスタッフを引き抜き、現代と同じ月曜日発売で週刊ポストを10年遅れで創刊した。
週刊誌の勢いは、私が週刊現代の編集長を辞める1997年まで続いた。「週刊誌黄金時代」だった。
それ以降、週刊誌だけではなく、出版社の売上も下降線をたどり、一度も部数が戻ることはなかった。
伊東編集長はこう続ける。
「その一方でPCやスマートフォンの普及により、ニュースや情報の流れかたは大きく変わりました。SNSの普及でフェイクニュースも増加し、うかうかしていると何が真実かわからなくなってしまう世の中です」
確かに、情報の流れ方は、私が辞めた後の30年で大きく変わった。だが、変わった時代に対応してこなかった週刊誌側の“怠慢”や“無策”が、時代に取り残されてしまった「大きな要因」だったことを忘却してはいけない。
「そんな混迷の時代に世界で起きていることを、これまでよりも少し深く、より丁寧に伝える。読んでおもしろく、ためになる――そしてなによりも老若男女を問わない読者の皆様に、発売日を心待ちにしていただけるような雑誌を目指します」(伊東編集長)
「おもしろくてためになる」というのは講談社の本や雑誌作りのモットーだが、こんな古臭いいい方でしか、新たにつくる雑誌のコンセプトをいい表せないところに、現代という雑誌の深刻な現状があるのだろう。
「隔週刊現代」は、そのうち「月刊現代」になり、紙媒体としての役割を終えるのだろう。
現代の“真似っ子”雑誌である週刊ポストも追随するはずだ。
行く行く現代は、ネットの「現代ビジネス」に吸収されていくのだろう。もしそうなら、隔週刊で出すことをスッパリやめて、ネット上で全く新しいDigital週刊誌を創刊したらどうだろう。
私は、1999年に講談社で「Web現代」というネットに特化した週刊誌を出したことがある。まだブロードバンドも普及していなかったため、この試みは失敗に終わったが、今ならできるはずだ。