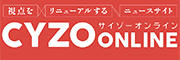この青木の考え方を「きれいごとすぎる」というのか、「タブーを恐れず、事実を追い求める」のがジャーナリストの仕事だと賛同するのか。難しい問題ではある。
次は、文春砲の「守護神」といわれる喜田村洋一弁護士のインタビュー。
喜田村は文藝春秋社の顧問弁護士である。私が現役時代からそうだったから長い。40年ぐらいになるのではないか。
その頃から、文春に喜田村ありきといわれていた。私がいた講談社にも顧問弁護士は2人いたが、一人は“ヤメ検”だった。この弁護士、検察の守護神のような人間で、相談に行っても我々編集部の意向など聞きもせず、「そんなことやれば告訴されるからやめておけ」と却下されることが多かった。
編集部に寄り添うなどということはなく、上の連中とゴルフばかりやっていた。つくづく文春がうらやましかったものだった。
間違いなく、文春が調査報道で名を挙げたのは、喜田村弁護士のバックアップがあったからである。
どんな仕事をしているのかと聞かれ、こう答えている。
「こういうテーマで取材しようと思っているが、名誉棄損にならないためには何にどう注意すべきか。こんな情報を得たが、これ書けますか、といった相談に答えることだ。重要なのは、題材、トピックの社会的公共性だと思っている。離婚や不倫も一般人なら別だが、政治家や公人なら意味を持ってくる。原稿もチェックする。言葉遣いにも節度が欲しい。そこまでやっているメディア弁護士はあまりいないのではないか」
そして報道の自由についてこう定義している。
「『報道の自由』とは、憲法21条(集会、結社、言論、出版その他一切の表現の自由の保証)を根拠にした、民主主義制度にとって圧倒的に大事な権利だ。政府の政策を知るのも、批判するのも、メディアを通じた情報提供が必要だ。個人の力では限界がある。、メディアという事実報道のプロ組織が、国民の目となり耳となる。これがなければ民主主義は成り立たないと思っている」