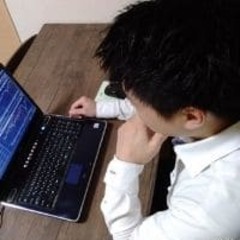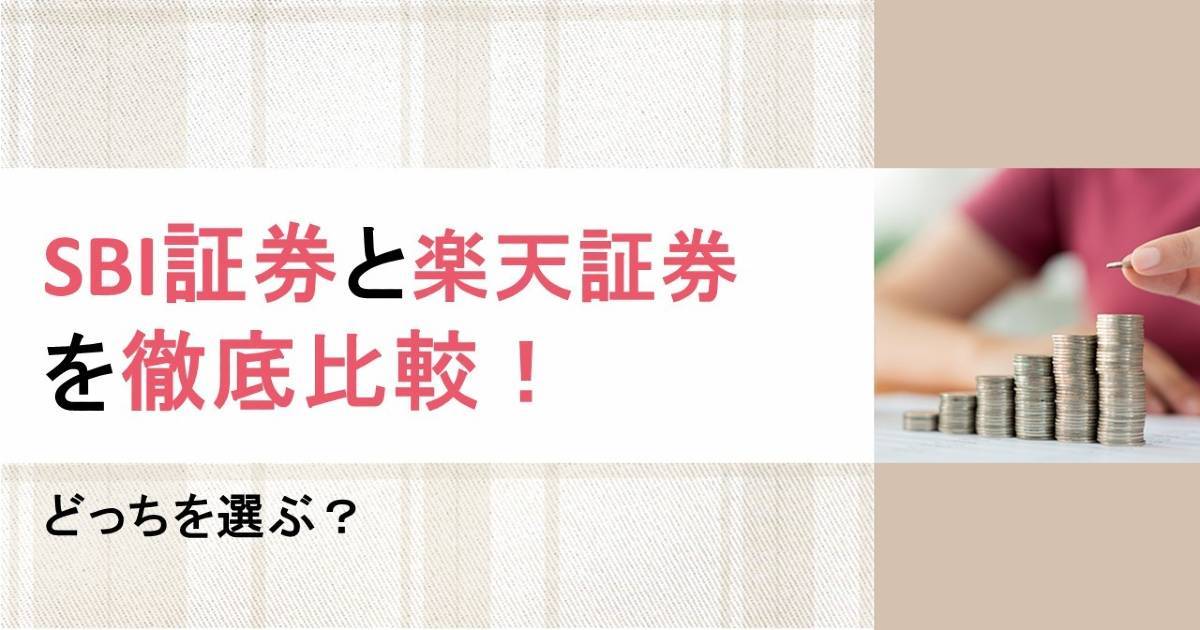
ネット証券大手2社であるSBI証券と楽天証券は1,000万口座を超えるシェアを誇り、多くの投資家から支持されています。両社は国内株式取引手数料無料、豊富な商品数など、基本的なサービスにはそれほど大きな差はありません。
しかし投資対象やアプリの使い勝手、ポイント制度など、細かく見ていくと違いがあります。
例えばSBI証券は外国株式の取り扱い数で楽天証券を上回り、IPO実績も豊富です。一方、楽天証券はアプリの使いやすさやポイント還元率で優れています。
投資スタイルや重視するポイントによって、どちらの証券会社が自分に適しているかは変わります。そこでこの記事ではSBI証券と楽天証券を13の項目で徹底比較し、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。
あなたにとって最適な証券会社を選び、より良い投資ライフを実現する参考にしてください。
目次
- SBI証券と楽天証券を徹底比較
- SBI証券と楽天証券を13の項目で詳細比較
- ①口座数 ——どちらも国内トップクラス
- ② 株式手数料 ——どちらも原則無料! 有料プランならSBI証券の方が安め
- ③ NISA成長投資枠 ―ほぼ互角、わずかにSBI証券に軍配
- ④ NISAつみたて投資枠 ―本数は互角ながら、積立頻度でSBIに白星
- ⑤ iDeCo ——商品が多いのはSBI、種類が多いのは楽天証券
- ⑥ 取扱商品 ―同水準 どちらも多様な資産に投資可能
- ⑦ 外国株 ——SBI証券が充実
- IPO実績 ——SBI証券の大勝
- ⑨ ポイント制度 ——ポイントの種類はSBIが圧倒、ポイント投資は楽天が豊富
- ⑩クレカ積立―最大ポイント付与率はSBI 引き下げには注意
- ⑪アプリの機能 ——楽天証券の方が高機能
- ⑫グループ銀行との連携―入金方法、優遇金利でSBIが有利
- ⑬キャンペーン ——両方の参加もおすすめ
- SBI証券と楽天証券のメリットを比較
- SBI証券と楽天証券のデメリットを比較
- SBI証券・楽天証券の口コミ
- Q&A
SBI証券と楽天証券を徹底比較

SBI証券と楽天証券を以下13項目で比較しました。
※以下の表では、比較の結果より優れている方に色付けをしています。色付けのない項目は、両者互角です。
| 証券会社 |  |
 |
|---|---|---|
| 口座数 | ◎ (1,245万口座)(※1) |
◎ (1,100万口座)(※2) |
| 株式手数料 | ◎ (原則無料)(※3) |
◎ (原則無料)(※4) |
| NISA成長投資枠 の取り扱い |
◎ | ◎ |
| NISAつみたて 投資枠のファンド数 |
◎ (225本) |
◎ (223本) |
| iDeCoの取扱本数 | ◎ (38本) |
◎ (36本) |
| 取扱商品 | ◎ | ◎ |
| 外国株 | ◎ (9ヵ国) |
〇 (6ヵ国) |
| IPO実績 (2023年) |
◎ (91銘柄) |
〇 (61銘柄) |
| ポイント | ◎ | ◎ |
| クレカ積立 | ◎ | ◎ |
| アプリの機能 | 〇 | ◎ |
| グループ銀行 の連携 |
◎ | 〇 |
| キャンペーン | ◎ | ◎ |
| 公式サイト |
口座を 作る |
口座を 作る |
※1.2024年3月(SBIネオトレード証券、FOLIOを含む)現在
※2.2024年4月現在
※3.インターネットコース(プランC含む)が対象(電子交付の設定が必須)
※4.ゼロコースが対象(RクロスおよびSORの利用同意が必須)。Rクロスとは条件が合致するとき楽天証券の顧客同士で売買を成立させる社内取引システムのこと。SORとは複数市場から条件に合致する最良の市場を選択して注文を執行する仕組み。
SBI証券の特徴として、外国株式の品揃えが豊富なこと、IPO実績が多いことが挙げられます。グループ銀行との連携サービスも手厚い傾向です。これらを重視するなら、SBI証券に口座を申し込みましょう。
一方、楽天証券の特徴はポイント投資の対象商品が多いこと、一つのアプリで日本とアメリカの株式を売買できることなどがあります。これらを重視するなら、楽天証券を選びましょう。
各項目の詳細は、次からの「SBI証券と楽天証券を13の項目で詳細比較」を参照してください。
SBI証券と楽天証券を13の項目で詳細比較

SBI証券と楽天証券の違いが分かるよう、さらに詳細に比較します。
 |
 |
|
| ①口座数 | 1,245万口座(※1) | 1,100万口座(※2) |
| ②株式手数料 | 原則無料(※3) | 原則無料(※4) |
| ③NISA 成長投資枠 |
【対象ファンド】 1,196本 【手数料無料の対象】 国内株式 米国株式 海外ETF 投資信託 |
【対象ファンド】 1,166本 【手数料無料の対象】 国内株式 米国株式 海外ETF 投資信託 |
| ④NISAつみたて 投資枠 |
225本 | 223本 |
| ⑤ iDeCo | 38本(投信37本) | 36本(投信35本) |
| ⑥取扱商品 | 【現物】 国内株式 外国株式 債券 投資信託 金・銀・プラチナ 【デリバティブ】 FX CFD 先物・オプション |
【現物】 国内株式 外国株式 債券 投資信託 金・銀・プラチナ 【デリバティブ】 FX CFD 先物・オプション |
| ⑦外国株 | 9ヵ国 【内訳】 米国 中国 シンガポール タイ マレーシア インドネシア 韓国 ロシア ベトナム |
6ヵ国 【内訳】 米国 中国 シンガポール タイ マレーシア インドネシア |
| ⑧IPO実績 (2023年) |
91銘柄 | 61銘柄 |
| ⑨ポイント | Vポイント、Pontaポイント、 dポイント、JALマイル、 PayPayポイント |
楽天ポイント、 楽天証券ポイント |
| ⑩クレカ積立 | 【対象カード】 三井住友カード 【ポイント付与率】 0.5%~5.0%(※5) |
【対象カード】 楽天カード 【ポイント付与率】 0.5%~1.0% |
| ⑪アプリの機能 | 米国株式の取引:〇(※6) 投資信託の取引:〇(※7) 画面カスタマイズ:× 【ニュース】 四季報 国内外の経済ニュース 個別銘柄ニュース 【銘柄検索】 スクリーニング ランキング テーマ チャート形状 株主優待 決算日 |
米国株式の取引:〇 投資信託の取引:× 画面カスタマイズ:〇 【ニュース】 四季報 国内外の経済ニュース 個別銘柄ニュース 日経テレコン マーケット動画解説 トウシル 【銘柄検索】 スクリーニング ランキング テーマ チャート形状 株主優待 業種 |
| ⑫グループ銀行 の連携 |
【住信SBIネット銀行】 入金手数料の無料:〇 自動入出金:〇 即時入金:〇 外貨入出金:〇 優遇金利:0.03%(通常0.02%) 【SBI新生銀行】 自動入出金:〇(※8) 即時入金:〇 外貨入出金:〇 優遇金利:0.15% (通常0.03%~0.15%) |
【楽天銀行】 入金手数料の無料:〇 自動入出金:〇 即時入金:〇 外貨入出金:× 優遇金利:0.1% (通常0.02%)(※9) |
| ⑬キャンペーン | 随時開催 | 随時開催 |
|
口座を 作る |
口座を 作る |
※1.2024年3月(SBIネオトレード証券、FOLIOを含む)現在
※2.2024年4月現在
※3.インターネットコース(プランC含む)が対象(電子交付の設定が必須)
※4.ゼロコースが対象(RクロスおよびSORの利用同意が必須)
※5.2024年11月買付分から0%~3.0%
※6.国内株アプリとは別アプリ
※7.投信積立のみ。国内株とは別アプリ
※8.投信積立代金の自動入金のみ
※9.優遇金利は300万円以下の部分が0.1%、300万円超の部分は0.04%
 |
 |
|
| ①口座数 | 1,245万口座(※1) | 1,100万口座(※2) |
| ②株式手数料 | 原則無料(※3) | 原則無料(※4) |
| ③NISA 成長投資枠 |
【対象ファンド】 1,196本 【手数料無料の対象】 国内株式 米国株式 海外ETF 投資信託 |
【対象ファンド】 1,166本 【手数料無料の対象】 国内株式 米国株式 海外ETF 投資信託 |
| ④NISAつみたて 投資枠 |
225本 | 223本 |
| ⑤ iDeCo | 38本(投信37本) | 36本(投信35本) |
| ⑥取扱商品 | 【現物】 国内株式 外国株式 債券 投資信託 金・銀・プラチナ 【デリバティブ】 FX CFD 先物・オプション |
【現物】 国内株式 外国株式 債券 投資信託 金・銀・プラチナ 【デリバティブ】 FX CFD 先物・オプション |
| ⑦外国株 | 9ヵ国 【内訳】 米国 中国 シンガポール タイ マレーシア インドネシア 韓国 ロシア ベトナム |
6ヵ国 【内訳】 米国 中国 シンガポール タイ マレーシア インドネシア |
| ⑧IPO実績 (2023年) |
91銘柄 | 61銘柄 |
| ⑨ポイント | Vポイント、Pontaポイント、 dポイント、JALマイル、 PayPayポイント |
楽天ポイント、 楽天証券ポイント |
| ⑩クレカ積立 | 【対象カード】 三井住友カード 【ポイント付与率】 0.5%~5.0%(※5) |
【対象カード】 楽天カード 【ポイント付与率】 0.5%~1.0% |
| ⑪アプリの機能 | 米国株式の取引:〇(※6) 投資信託の取引:〇(※7) 画面カスタマイズ:× 【ニュース】 四季報 国内外の経済ニュース 個別銘柄ニュース 【銘柄検索】 スクリーニング ランキング テーマ チャート形状 株主優待 決算日 |
米国株式の取引:〇 投資信託の取引:× 画面カスタマイズ:〇 【ニュース】 四季報 国内外の経済ニュース 個別銘柄ニュース 日経テレコン マーケット動画解説 トウシル 【銘柄検索】 スクリーニング ランキング テーマ チャート形状 株主優待 業種 |
| ⑫グループ銀行 の連携 |
【住信SBIネット銀行】 入金手数料の無料:〇 自動入出金:〇 即時入金:〇 外貨入出金:〇 優遇金利:0.03%(通常0.02%) 【SBI新生銀行】 自動入出金:〇(※8) 即時入金:〇 外貨入出金:〇 優遇金利:0.15% (通常0.03%~0.15%) |
【楽天銀行】 入金手数料の無料:〇 自動入出金:〇 即時入金:〇 外貨入出金:× 優遇金利:0.1% (通常0.02%)(※9) |
| ⑬キャンペーン | 随時開催 | 随時開催 |
|
口座を 作る |
口座を 作る |
※1.2024年3月(SBIネオトレード証券、FOLIOを含む)現在
※2.2024年4月現在
※3.インターネットコース(プランC含む)が対象(電子交付の設定が必須)
※4.ゼロコースが対象(RクロスおよびSORの利用同意が必須)
※5.2024年11月買付分から0%~3.0%
※6.国内株アプリとは別アプリ
※7.投信積立のみ。国内株とは別アプリ
※8.投信積立代金の自動入金のみ
※9.優遇金利は300万円以下の部分が0.1%、300万円超の部分は0.04%
「自分のこだわりたい項目ではどちらが有利なのか?」をチェックしてから口座開設をするといいでしょう。
①口座数 ——どちらも国内トップクラス
口座数はSBI証券と楽天証券のどちらもトップクラスです。SBI証券はグループ全体で1,200万超の口座を持っており、楽天証券は単体で1,100万口座を抱えています。
- SBI証券:1,245万口座(2024年3月)(※1)
- 楽天証券:1,100万口座(2024年4月)
- 野村證券:551万口座(2024年4月)(※2)
- 大和証券:312万口座(2024年3月)(※2)
- マネックス証券:261万口座(2024年4月)
※出典:SBI証券、楽天証券、野村證券、大和証券、マネックス証券
※1.SBIネオトレード証券、FOLIOを含む
※2.残あり口座のみ
NISA口座でも、SBI証券と楽天証券はトップクラスです。SBI証券は2024年3月で476万口座、楽天証券は2023年末で515万口座を持っています。
日本証券業協会によると、主要な証券会社10社のNISA口座は2024年2月で約1,400万口座でした(出典:日本証券業協会 NISA口座の開設・利用状況(2024年3月))。単純に考えれば、SBI証券と楽天証券の2社だけで7割のシェアを持つことになります。
「人気が高く多くの人が使っている証券会社の方が安心だ」と考えている人にとっては、SBI証券でも楽天証券でも、十分な口座数でしょう。
② 株式手数料 ——どちらも原則無料! 有料プランならSBI証券の方が安め
 |
 |
|---|---|
| 原則無料(※1) | 原則無料(※2) |
※2.ゼロコースが対象(RクロスおよびSORの利用同意が必須)
SBI証券と楽天証券はいずれも手数料無料で株式を売買できます。
SBI証券の場合、電子交付サービス(※)に同意すれば株式手数料が無料となります。 ※電子交付サービス:各種書面を郵送に代えてウェブ上で閲覧できるサービス
ただし対象はインターネットコース(プランC含む)のみです。ダイレクトコースやIFAコース、対面コースを選択している人は対象外です。
楽天証券の場合、手数料コースにゼロコースを指定すれば株式手数料が無料となります。なお、ゼロコースを指定するにはRクロス(※)およびSOR(※)の利用同意が必須です。
※Rクロス:条件が合致するとき楽天証券の顧客同士で売買を成立させる社内取引システム
※SOR:複数市場から条件に合致する最良の市場を選択して注文を執行する仕組み
◾️手数料無料の条件を満たせなかった場合は、SBI証券と楽天証券どちらが安い?
・定額系プランで1日の売買代金が100万円を超える場合……SBI証券の方が安い
・定額系プランで1日の売買代金が100万円以下の場合……両社とも0円
・1取引プランの場合……両社の金額に違いはない
有料の株式手数料には、1日の取引金額の合計で手数料を計算する「定額系プラン」と、取引1回ごとに計算する「1取引ごとプラン」とがあります。
このうち、「定額系プラン」で1日の売買代金が100万円を超えるとSBI証券の方が手数料が安くなります。
1日の売買代金が100万円以下の場合、両社ともに手数料は無料です。
 |
 |
|
| 100万円まで | 0円 | 0円 |
| 200万円まで | 1,238円 | 2,200円 |
| 300万円まで | 1,691円 | 3,300円 |
| 以降100万円ごとに | 295円 | 1,100円 |
| 公式サイト |
口座を 作る |
口座を 作る |
「1取引ごとプラン」の場合、SBI証券と楽天証券に差はありません。例えば売買代金が50万円なら275円かかります。買いと売りの往復で手数料は550円になります。
③ NISA成長投資枠 ―ほぼ互角、わずかにSBI証券に軍配
 |
 |
|---|---|
| 【対象ファンド】 1,196本 【手数料無料の対象】 国内株式 米国株式 海外ETF 投資信託 |
【対象ファンド】 1,166本 【手数料無料の対象】 国内株式 米国株式 海外ETF 投資信託 |
NISA成長投資枠の取り扱いはSBI証券と楽天証券で互角です。
取扱商品の数や手数料無料の対象商品に大きな差はありません。ただし詳細に比べるとSBI証券の方がわずかに優れているといえそうです。
NISA成長投資枠では国内株式や外国株式、投資信託に投資が可能です。
成長投資枠の対象商品は、証券取引所に上場している株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)や、株式投資信託等です。ただし、①整理銘柄・監理銘柄に指定されている株式、②信託期間が 20 年未満、高レバレッジ型及び毎月分配型の投資信託等は対象から除外されています。
引用:日本証券業協会 2024年以降のNISAに関するQ&A
SBI証券と楽天証券では以下の商品を取り扱っています。取り扱い銘柄の国の多様性や数はほぼ同水準ですが、SBI証券の方が楽天証券をやや上回ります。
| 証券会社 |  |
 |
|---|---|---|
| 国内株式 | 東証、名証、福証、札証 | 東証、名証 |
| 単元未満株 | 東証(※1) | 東証 |
| 外国株式 | 9ヵ国 | 6ヵ国 |
| 海外ETF | 4ヵ国 | 3ヵ国 |
| 投資信託 | 1,196本 | 1,166本 |
| 公式サイト |
口座を 作る |
口座を 作る |
成長投資枠では取引手数料がかかることがあります。しかしSBI証券と楽天証券では、米国以外の外国株式を除き、原則無料で取引できます。
ただし楽天証券の場合、単元未満株のリアルタイム取引は0.22%のスプレッドが別途かかります。この点を踏まえれば、手数料でもSBI証券の方がわずかに有利といえるでしょう。
| 証券会社 |  |
 |
|---|---|---|
| 国内株式 | 〇 | 〇 |
| 単元未満株 | 〇 | 〇(※1) |
| 米国株式 | 〇 | 〇 |
| 米国以外の 外国株式 |
― | ― |
| 海外ETF | 〇 | 〇 |
| 投資信託 | 〇 | 〇 |
| 公式サイト |
口座を 作る |
口座を 作る |
④ NISAつみたて投資枠 ―本数は互角ながら、積立頻度でSBIに白星
つみたて投資枠の取扱本数は互角ですが、積立頻度の選択肢の多さからSBI証券の方が有利です。SBI証券では毎月・毎週・毎日と3つパターンを選べます(楽天証券は2パターン)。
◾️NISAつみたて投資枠の取扱本数
つみたて投資枠の対象商品の取り扱いは、SBI証券が225本、楽天証券は223本なので差はほぼないといえるでしょう。
- SBI証券:225本
- 楽天証券:223本
なおNISAのつみたて投資枠では、金融庁の基準を満たした一定の投資信託に投資が可能です。2024年5月現在で281本が対象となっています(ETF除く。出典:金融庁 つみたて投資枠対象商品)。SBI証券も楽天証券も、つみたて投資枠の全対象商品のほとんどを取り扱っていると言えるでしょう。
◾️ NISAつみたて投資枠の積立頻度
ただし積立頻度はSBI証券の方が優れています。
SBI証券では毎日・毎週・毎月の3コースから選べます。一方、楽天証券が選べる積立頻度は毎日・毎月の2コースです。
より多くの選択肢から積立頻度を選びたい人は、SBI証券の方がいいでしょう。
⑤ iDeCo ——商品が多いのはSBI、種類が多いのは楽天証券
iDeCoの取扱商品数は、SBI証券が楽天証券を上回ります。
しかし楽天証券は投資信託の種類が豊富です。具体的には、SBI証券はインデックス型ファンドが多く、楽天証券は全カテゴリーの投資信託を取り扱っています。
◾️iDeCoの取扱商品数
iDeCoの取扱商品数を比較すると、SBI証券の方がやや多いです。具体的には、SBI証券は38本(投信37本)、楽天証券は36本(投信35本)を取り扱っています。
【iDeCoの取扱商品の数】
◾️iDeCoの商品種類
iDeCoの取扱商品のうち、インデックス型ファンドが多いのはSBI証券でした。運用コストはインデックス型の方が安い傾向があり、長期の運用に向いています。
ただし、投資信託の種類は楽天証券の方が幅広くカバーしています。
確定拠出年金教育協会によると、楽天証券はiDeCoで全カテゴリーの投資信託を取り扱っています。しかしSBI証券のiDeCoにはハイイールド債券型の投資信託がありません。
| 証券会社 |  |
 |
|---|---|---|
| 国内株式 | 6本 | 6本 |
| 先進国株式 | 13本 | 10本 |
| 新興国株式 | 2本 | 1本 |
| 国内債券 | 1本 | 2本 |
| 先進国債券 | 3本 | 2本 |
| 新興国債券 | 1本 | 1本 |
| ハイイールド債券 | ― | 1本 |
| バランス型 | 8本 | 8本 |
| REIT | 2本 | 3本 |
| 金 | 1本 | 1本 |
| 公式サイト |
口座を 作る |
口座を 作る |
※投資信託のカテゴリーは確定拠出年金教育協会から引用
SBI証券のiDeCoにはハイイールド債券型の投資信託はありません。一方、楽天証券はアメリカのハイイールド債券に投資する「みずほUSハイイールドファンド<DC年金>」を取り扱っています。
- LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンドを通して、主に米国の米国ドル建て高利回り債(ハイイールド債)に投資するファンド
- ベンチマークはICE BofA・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)
初心者でリスクを取りたくない場合はSBI証券を、リスク覚悟で高利回りを望むなら楽天証券のiDeCoを選ぶのがいいでしょう。
⑥ 取扱商品 ―同水準 どちらも多様な資産に投資可能
 |
 |
|---|---|
| 【現物】 国内株式 外国株式 債券 投資信託 金・銀・プラチナ 【デリバティブ】 FX CFD 先物・オプション |
【現物】 国内株式 外国株式 債券 投資信託 金・銀・プラチナ 【デリバティブ】 FX CFD 先物・オプション |
SBI証券と楽天証券で、取扱商品に差はほとんどありません。いずれもラインアップは豊富で、どちらを選んでもさまざまな取引が可能です。
現物については、両社とも国内外の株式や債券、投資信託を取り扱っています。国内株式についてはSBI証券と楽天証券の双方で単元未満株(1株単位)の取引が可能です。
両社は、金や銀、プラチナといった貴金属の金融商品もカバーしています。
信用取引やデリバティブといった複雑な商品でも、取り扱う銘柄の種類や数はほぼ同じです。ただし詳細に見ると、やや異なる点はあります。
海外先物(シンガポール)とバイナリーオプション(※)は楽天証券で取り扱いがあります。CFD(差金決済取引)について、SBI証券は株式市場などの取引所で取引される「取引所CFD(くりっく株365)」を、楽天証券は、顧客と証券会社が直接取引する「店頭CFD」を扱います。
※バイナリーオプション:為替が一定期間後に指定したレートを上回るか下回るか予測する取引
| 証券会社 |  |
 |
|---|---|---|
| 信用取引 (国内・米国) |
〇 | 〇 |
| 店頭FX | 〇 | 〇 |
| 取引所FX (くりっく365) |
― | ― |
| 店頭CFD | ― | 〇 |
| 取引所CFD (くりっく株365) |
〇 | ― |
| 株価指数・ 商品先物 |
〇 | 〇 |
| 海外先物 (シンガポール) |
― | 〇 |
| 日経225 オプション |
〇 | 〇 |
| バイナリー オプション |
― | 〇 |
| 公式サイト |
口座を 作る |
口座を 作る |
⑦ 外国株 ——SBI証券が充実
 |
 |
|---|---|
| 9ヵ国 【内訳】 米国 中国 シンガポール タイ マレーシア インドネシア 韓国 ロシア ベトナム |
6ヵ国 【内訳】 米国 中国 シンガポール タイ マレーシア インドネシア |
外国株の取り扱いはSBI証券の方が優れています。
SBI証券は9ヵ国の株式に投資できます。一方、楽天証券は6ヵ国です。SBI証券が取り扱う外国株は楽天証券が取り扱う株式を完全に網羅しています。銘柄数においても、SBI証券が楽天証券を大きく上回っています。
ただし、中国株に関しては楽天証券の方が優位です。
| 証券会社 |  |
 |
|---|---|---|
| アメリカ (ADR除く) |
4,451銘柄 | 4,025銘柄 |
| 中国 | 1,274銘柄 | 1,538銘柄 |
| シンガポール | 38銘柄 | 35銘柄 |
| インドネシア | 74銘柄 | 70銘柄 |
| タイ | 78銘柄 | 68銘柄 |
| マレーシア | 44銘柄 | 42銘柄 |
| ロシア | 29銘柄 | ― |
| 韓国 | 68銘柄 | ― |
| ベトナム | 295銘柄 | ― |
| 合計 | 6,351銘柄 | 5,778銘柄 |
| 公式サイト |
口座を 作る |
口座を 作る |
海外ETFの取り扱いもSBI証券の方が充実しています。
SBI証券は4ヵ国の海外ETFを売買できます。一方の楽天証券は3ヵ国にとどまり、しかもその3ヵ国はSBI証券でも投資可能です。
もっとも、銘柄数では両社に大きな差はありません。
| 証券会社 |  |
 |
|---|---|---|
| アメリカ | 404銘柄 | 399銘柄 |
| 中国 | 30銘柄 | 29銘柄 |
| シンガポール | 12銘柄 | 16銘柄 |
| 韓国 | 2銘柄 | ― |
| 合計 | 448銘柄 | 444銘柄 |
| 公式サイト |
口座を 作る |
口座を 作る |
IPO実績 ——SBI証券の大勝
IPOの取り扱いはSBI証券が圧倒しています。
SBI証券は2023年までの5年間で471銘柄のIPOを取り扱いました。対して楽天証券は264銘柄にとどまっています。各年で見ても、IPOの実績で楽天証券はSBI証券を上回ったことはありません。
| 証券会社 |  |
 |
|---|---|---|
| 2019年 | 84銘柄 | 26銘柄 |
| 2020年 | 85銘柄 | 38銘柄 |
| 2021年 | 122銘柄 | 74銘柄 |
| 2022年 | 89銘柄 | 65銘柄 |
| 2023年 | 91銘柄 | 61銘柄 |
| 合計 | 471銘柄 | 264銘柄 |
| 公式サイト |
口座を 作る |
口座を 作る |
⑨ ポイント制度 ——ポイントの種類はSBIが圧倒、ポイント投資は楽天が豊富
SBI証券や楽天証券は投資の取引額や手数料に応じてポイントが貯まります。
貯まるポイントの種類はSBI証券の方が優位です。一方、投資対象商品で比べると、楽天証券はSBI証券よりバリエーションが多いです。
貯まるポイントの種類、ポイントの貯め方、ポイント投資の3つに分けて解説します。
貯まるポイントの種類
貯まるポイントの種類が多いのはSBI証券です。
VポイントやPontaポイントといった5つの共通ポイントを貯められます。楽天証券の場合、楽天ポイントまたは楽天証券ポイントが貯まります。
| 証券会社 |  |
 |
|---|---|---|
| Vポイント、 SBI証券限定Vポイント |
〇 | ― |
| Pontaポイント | 〇 | ― |
| dポイント | 〇 | ― |
| JALマイル | 〇 | ― |
| PayPayポイント | 〇 | ― |
| 楽天ポイント、 楽天証券ポイント |
― | 〇 |
| 公式サイト |
口座を 作る |
口座を 作る |
ポイントの貯め方
SBI証券と楽天証券はいずれも、国内株式や投資信託など、取引に応じたポイントが付与されます。両者のポイントの貯まり方や、付与率には違いがあります。
SBI証券では新規口座の開設もポイント付与の対象です。また楽天証券は外国株式や先物・オプションの取引、電子マネー(楽天キャッシュ)積み立てでもポイントが貯まります。
| 証券会社 |  |
 |
|---|---|---|
| 新規口座開設 | 一律100ポイント | ― |
| 国内株式 | 手数料の1.1% (※2) |
手数料の1.0% (※3) |
| 外国株式 | ― | 手数料の1.0% (※4) |
| 先物・オプション | ― | 手数料の1.0% (※4) |
| 投資信託 | 残高の最大0.25% (年率) |
残高の最大0.053% (年率)(※5)(※6) |
| クレカ積立 (投信) |
決済額の最大5.0% (※7) |
決済額の最大1.0% |
| 金・銀・プラチナ | 手数料の1.0% | 手数料の1.0% (※4) |
| クレカ積立 (金・銀・プラチナ) |
― | 決済額の0.5% |
| 電子マネー積立 (投信) |
― | チャージ額の0.5% |
| 公式サイト |
口座を 作る |
口座を 作る |
なお、投資信託の保有に対するポイント付与は、SBI証券と楽天証券で仕組みが異なります。
SBI証券は投資信託の月間平均保有額に応じてポイントを付与する「投信マイレージ」というサービスを提供しています。投信マイレージのポイント付与率は、銘柄と投資信託の保有額に応じて以下のように決まります。
| 保有額 | 投信保有額 1,000万円未満 |
投信保有額 1,000万円以上 |
|---|---|---|
| 通常銘柄 | 0.10% | 0.20% |
| SBIプレミアム セレクト銘柄 |
0.15% | 0.25% |
| その他の指定銘柄 | 指定の付与率 | 指定の付与率 |
※JALマイルはいずれも2分の1
投信マイレージのポイント付与率が上昇するSBIプレミアムセレクト銘柄は以下の通りです。なおSBIプレミアムセレクト銘柄は3ヵ月ごとに見直されます。
- 日本ニューテクノロジー・オープン
- 情報エレクトロニクスファンド
- 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
- ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
- 明治安田セレクト日本株式ファンド
- モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
- 日経平均高配当利回り株ファンド
- アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
- インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
- フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
- フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)
- ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)
- netWin GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
- グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
- HSBCインド・インフラ株式オープン
※SBI証券(2024年5月23日現在)
楽天証券は、投資信託の保有に対するポイント付与サービスは「投信残高ポイントプログラム」と「資産形成ポイント」の2つです。
投信残高ポイントプログラムでは、対象銘柄の月間平均保有額に対しポイントが毎月付与されます。対象銘柄とポイント付与率は以下の通りです。
| 銘柄 | ポイント付与率 (年率) |
|---|---|
| 楽天・オールカントリー株式 インデックス・ファンド |
0.017% |
| 楽天・S&P500 インデックス・ファンド |
0.028% |
| 楽天・先進国株式(除く日本) インデックス・ファンド |
0.033% |
| 楽天・日経225 インデックス・ファンド |
0.053% |
| 楽天・NASDAQ-100 インデックス・ファンド |
0.050% |
| 楽天・SOX インデックス・ファンド |
0.050% |
「資産形成ポイント」のプログラムでは、投資信託の保有残高が初めて一定額に到達した場合にのみポイントが付与されます。保有残高は月末で毎月判定されます。保有残高が10万円、30万円、50万円……と一定額に到達するたびにポイントが付与される仕組みです。
残高が2,000万円に到達すると、最後のポイントが付与されます。累計で2,090ポイントが進呈され、以降は残高が増えてもポイントは付与されません。
- 月末の投信残高が初めて10万円に到達:10ポイント
- 同30万円:30ポイント
- 同50万円:50ポイント
- 同100万円:100ポイント
- 同200万円:100ポイント
- 同300万円:100ポイント
- 同400万円:100ポイント
- 同500万円:100ポイント
- 同1,000万円:500ポイント
- 同1,500万円:500ポイント
- 同2,000万円:500ポイント
※出典:楽天証券(2024年5月23日現在)
ポイント投資
ポイント投資とはポイントを使って実際の金融商品を購入できるサービスです。ポイント投資の対象銘柄については楽天証券の方が多くの選択肢があります。
SBI証券と楽天証券でポイント投資できる商品は国内株式と投資信託などです。楽天証券の場合、さらに米国株式とバイナリーオプションも対象です。
⑩クレカ積立―最大ポイント付与率はSBI 引き下げには注意
SBI証券と楽天証券ではカード券種によってポイント付与率が異なります。最大ポイント付与率はSBI証券が楽天証券を上回っています。
クレカ積立とは投資信託の積み立てをクレジットカードで決済できるサービスで、決済額に対してポイントが付与されます。
SBI証券は三井住友カード、楽天証券は楽天カードに対応しています。決済可能額は、ともに月10万円までです。
楽天証券のクレカ積立は積み立てる銘柄によって、ポイント付与率が異なります。
代行手数料が0.4%以上の銘柄を積み立てる場合、ポイント付与率は一律1.0%となります。代行手数料とは信託報酬のうち楽天証券が受け取る部分です。
例えばeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)やeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)は代行手数料が0.4%未満なので、楽天カードのクレカ積立におけるポイント付与率は0.5%となります。
代行手数料は、楽天証券の銘柄ごとのWebサイトで確認できます。
| 代行手数料 | 代行手数料0.4%未満 | 代行手数料0.4%以上 |
|---|---|---|
| 楽天カード | 0.5% | 1.0% |
| 楽天ゴールドカード | 0.75% | 1.0% |
| 楽天プレミアムカード | 1.0% | 1.0% |
2024年11月買付分からは、ポイント付与率の判定基準に年間カード利用額が追加されます。
年間カード利用額が10万円に満たない場合、カード券種によってはポイントが付与されません。
| 10万円未満 | 10万円以上 | 100万円以上 | 300万円以上 | 500万円以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
 三井住友カード (NL) |
― | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
 三井住友カード ゴールド(NL) |
― | 0.75% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
 三井住友カード プラチナプリファード |
1.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 3.0% |
※金額は年間カード利用額
クレカ積立における毎月の積立額が約8,400円に満たず、かつ、クレカ積立以外にカードを利用しないなら、楽天証券を選んだ方がよいでしょう。楽天証券のクレカ積立なら、少なくとも0.5%以上のポイントを受け取れます。
⑪アプリの機能 ——楽天証券の方が高機能
スマートフォンアプリの機能は、楽天証券はSBI証券より機能が充実しています。
SBI証券と楽天証券は国内株式アプリとしてそれぞれ「SBI証券 株アプリ」と「iSPEED(アイスピード)」を提供しています。
各アプリで取引できる商品は以下の通りです。両社とも国内株式と単元未満株の取引に対応しています。楽天証券はさらに同一アプリで米国株式の取引も可能です。
| 証券会社とアプリ名 | SBI証券 (SBI証券 株アプリ) |
楽天証券 (iSPEED) |
|---|---|---|
| 国内株式 | 〇 | 〇 |
| 単元未満株 | 〇 | 〇 |
| 米国株式 | ―(※1) | 〇 |
| 投資信託(積立) | ―(※2) | ― |
投資情報も、楽天証券にやや分があるといえるでしょう。
SBI証券と楽天証券は、どちらも国内株式アプリで多くの投資情報を提供しています。情報ベンダー各社のニュースや、東洋経済新報社の「四季報」などが閲覧可能です。楽天証券はさらに楽天証券版日経テレコンの利用も可能です。
⑫グループ銀行との連携―入金方法、優遇金利でSBIが有利
 |
 |
|---|---|
| 【住信SBIネット銀行】 入金手数料の無料:〇 自動入出金:〇 即時入金:〇 外貨入出金:〇 優遇金利:0.03% (通常0.02%) 【SBI新生銀行】 自動入出金:〇(※8) 即時入金:〇 外貨入出金:〇 優遇金利:0.15% (通常0.03%~0.15%) |
【楽天銀行】 入金手数料の無料:〇 自動入出金:〇 即時入金:〇 外貨入出金:× 優遇金利:0.1% (通常0.02%)(※9) |
グループ銀行との連携サービスはSBI証券の方が手厚い傾向です。外貨の入出金や優遇金利といった面においても、SBI証券が優位に立っています。
SBI証券と楽天証券はそれぞれ以下のグループ銀行との連携サービスを提供しています。
・SBI証券……住信SBIネット銀行、SBI新生銀行
・楽天証券……楽天銀行
サービスを利用すれば手数料無料で証券口座に入金できます。
連携銀行からの入金方法は以下の通りです。
| 証券会社と 銀行の組み合わせ |
SBI証券×住信SBI | SBI証券×SBI新生 | 楽天証券×楽天銀行 |
|---|---|---|---|
| 自動入出金 | 〇 | 〇 (※1) |
〇 |
| 即時入金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 外貨即時入金 | 〇 | 〇 | ― |
| 外貨出金 | 〇 | 〇 | ― |
SBI証券は外貨での資金を証券口座に即座に反映させる「外貨即時入金」に対応していますが、楽天証券は対応していません。
なお、為替手数料については、SBI証券も楽天証券も2023年末に無料化しています。

SBI証券の米ドルの為替手数料は、かつて住信SBIネット銀行やSBI新生銀行より割高でした。しかしSBI証券は2023年12月、米ドルの為替手数料を原則無料化しました(システム完了まではキャッシュバックで対応)。
従来は住信SBIネット銀行やSBI新生銀行で米ドルを購入し、その後SBI証券へ入金する方が低コストでした。現在はSBI証券で直接米ドルを購入した方がお得です。
なお、楽天証券も2023年12月に米ドル為替手数料を撤廃しています。
若山卓也(ファイナンシャル・プランナー)
グループ銀行の優遇金利は以下の通りです。利率が高い順にSBI新生銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行となっています。
SBI新生銀行を連携させるなら、優遇金利はSBI証券の方が優れているといえます。
| 証券会社と銀行の 組み合わせ |
SBI証券×住信SBI | SBI証券×SBI新生 | 楽天証券×楽天銀行 |
|---|---|---|---|
| 通常金利 | 0.02% | 0.03%~0.15% | 0.02% |
| 優遇金利 | 0.03% | 0.15% | 0.10%(※1) |
※1.300万円以下の部分(300万円超の部分は0.04%)
⑬キャンペーン ——両方の参加もおすすめ
SBI証券と楽天証券はいずれもキャンペーンの開催に積極的です。例えば2024年7月現在で以下のようなキャンペーンを展開しています。
| キャンペーン名 | 概要 |
|---|---|
| iDeCoならSBI証券 キャンペーン |
iDeCoの開設と拠出でAmazonギフトカードが 抽選で当たる(2024年8月5日まで) |
| ワンダフル キャンペーン |
対象債券の購入で現金が抽選で当たる (対象債券の完売まで) |
| 【SBI証券 FX】 ダブルでお得なキャンペーン |
FXで対象通貨ペアのスワップポイントの増量および スプレッドの縮小(2024年8月1日まで) |
| キャンペーン名 | 概要 |
|---|---|
| 純金プラチナキャンペーン | 金・銀・プラチナの購入で純金・純プラチナ・ 純銀コインが抽選で当たる(2024年8月19日まで) |
| iDeCoでラッキー555 | iDeCo開設でポイントが抽選で当たる (2024年7月31日まで) |
| 信用取引デビュー 応援プログラム |
信用取引口座の開設でポイント進呈(常設) |
できるだけ多くのキャンペーンに参加したいなら、SBI証券と楽天証券の両方で口座を開設するのも手です。証券口座はいくつ開設してもかまいません。
SBI証券と楽天証券のメリットを比較

SBI証券と楽天証券には、商品ラインアップの豊富さや取引手数料の安さなど、共通のメリットがあります。
またSBI証券は貯まるポイントの選択肢が多く、IPO実績も豊富な点が魅力です。一方の楽天証券は日経テレコンが無料で利用でき、ポイント投資の対象商品が多い点が利点といえるでしょう。
以下、両者に共通するメリットと、SBI証券と楽天証券それぞれのメリットに分けて紹介します。
SBI証券と楽天証券に共通するメリット
SBI証券と楽天証券の両方に共通するメリットには以下の2つが挙げられます。
- 商品の取り扱いが豊富
- 取引手数料が無料の商品が多い
SBI証券と楽天証券はどちらも商品のラインアップが豊富です。国内外の株式や投資信託、金・銀・プラチナといった種々の商品が用意されています。
各商品の取扱銘柄も充実しています。例えば投資信託の場合、SBI証券と楽天証券はどちらも2,500本以上を取り扱っています。これは主要なネット証券で抜きんでています。
NISA対象銘柄の取り扱いもトップクラスです。
 |
 |
 |
 |
 |
|
| 全体 | 2,567本 | 2,562本 | 1,777本 | 1,811本 | 1,882本 |
| NISA成長 投資枠 |
1,196本 | 1,166本 | 1,150本 | 1,045本 | 1,102本 |
| NISAつみたて 投資枠 |
225本 | 223本 | 228本 | 221本 | 230本 |
| 公式サイト |
口座を 作る |
口座を 作る |
口座を 作る |
口座を 作る |
口座を 作る |
外国株式も取り扱いも充実しています。SBI証券は9ヵ国、楽天証券は6ヵ国の外国株式に投資できます。一方、他の主要ネット証券は1ヵ国か2ヵ国にとどまっています。
 |
 |
 |
 |
 |
|
| アメリカ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中国 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― |
| シンガポール | 〇 | 〇 | ― | ― | ― |
| インドネシア | 〇 | 〇 | ― | ― | ― |
| タイ | 〇 | 〇 | ― | ― | ― |
| マレーシア | 〇 | 〇 | ― | ― | ― |
| ロシア | 〇 | ― | ― | ― | ― |
| 韓国 | 〇 | ― | ― | ― | ― |
| ベトナム | 〇 | ― | ― | ― | ― |
| 公式サイト |
口座を 作る |
口座を 作る |
口座を 作る |
口座を 作る |
口座を 作る |
米国株式の取扱銘柄数は以下の通りです。SBI証券と楽天証券は、やはり比較的多くの銘柄を取り扱っていることがわかります。
- SBI証券:4,774銘柄
- 楽天証券:4,340銘柄
- マネックス証券:4,491銘柄
- auカブコム証券:1,890銘柄
- 松井証券:3,669銘柄
※出典:SBI証券、楽天証券、マネックス証券、auカブコム証券、松井証券(2024年5月23日現在)
取引手数料が無料の商品が多いメリットも、SBI証券と楽天証券に共通しています。
SBI証券と楽天証券は国内株式(単元未満株含む)や投資信託、米ドルの為替手数料を原則無料化しています。主要なネット証券と比較しても、無料で取引できる商品の数はトップクラスです。
 |
 |
 |
 |
 |
|
| 国内株式 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― |
| 単元未満株 | 〇 | 〇 (※1) |
― (※2) |
― | 取扱なし |
| 投資信託 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 米国株式 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 中国株式 | ― | ― | ― | 取扱なし | 取扱なし |
| 海外ETF | ― | ― | ― | ― | ― |
| 為替手数料 (米ドル) |
〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 |
| 公式サイト |
口座を 作る |
口座を 作る |
口座を 作る |
口座を 作る |
口座を 作る |
なおNISA口座の場合は、以下のようにその他のネット証券も多くの商品で取引手数料を無料にしています。
 |
 |
 |
 |
 |
|
| 国内株式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 単元未満株 | 〇 | 〇 (※1) |
〇 | ― | 取扱なし |
| 投資信託 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 米国株式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中国株式 | ― | ― | 〇 | 取扱なし | 取扱なし |
| 海外ETF | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 為替手数料 (米ドル) |
〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 |
| 公式サイト |
口座を 作る |
口座を 作る |
口座を 作る |
口座を 作る |
口座を 作る |
SBI証券のメリット

SBI証券のメリットは主に以下の3つです。
- 貯まるポイントを選べる
- IPOの実績が豊富
- 積立コースの選択肢が多い
SBI証券では貯められるポイントを5種類(Vポイント、Pontaポイント、dポイント、JALマイル、Pontaポイント)から自由に選べます。あとからポイントの種類を変更することも可能です。変更は即時に反映されます。
取引で貯められるポイントは以下の通りです。
| Vポイント | Pontaポイント | dポイント | JALマイル | PayPayポイント | |
| 国内株式の取引 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 投資信託の保有 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 金・銀・ プラチナの取引 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 新規口座開設 | 〇 (※1) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| クレカ積立 | 〇 | ― | ― | ― | ― |
| 紹介 | 〇 | ― | 〇 | ― | ― |
SBI証券にはIPOの取り扱いが豊富という魅力もあります。2021年度(2021年4月~2022年3月)は117銘柄を取り扱いました。SBI証券によれば、これは業界で最多です。
- 1. SBI証券:117銘柄
- 2. SMBC日興証券:76銘柄
- 3. みずほ証券:75銘柄
- 4. 楽天証券:70銘柄
- 5. 野村證券:62銘柄
出典:SBI証券

SBI証券ではIPOの抽選に外れると「IPOチャレンジポイント」が1ポイント付与されます。IPOチャレンジポイントを使用すると配分を受けやすくなります。
SBI証券のIPOでは全体の30%をIPOチャレンジポイントの使用が多い順に割り当てます。ポイントを使用して抽選に外れた場合、使用量+1ポイントが再び付与されます。
つまり応募を継続すれば、抽選に当たるまでIPOチャレンジポイントは増え続け、当選確率は上昇してくことになります。
若山卓也(ファイナンシャル・プランナー)
投信積立のコースが多いこともSBI証券のメリットです。
SBI証券の投信積立は積立頻度を最大5コース(毎日・毎週・毎月・複数日・隔月)から選べます。一方、楽天証券はNISAつみたて投資枠のみ2コース(毎月・毎日)から選べ、その他の口座では毎月しか選べません。
| 課税口座 | NISA成長 投資枠 |
NISAつみたて 投資枠 |
|
| 毎日 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 毎週 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 毎月 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 複数日 | 〇 | 〇 | ― |
| 隔月 | 〇 | 〇 | ― |
※クレカ積立は毎月のみ
楽天証券のメリット

楽天証券のメリットは以下の通りです。
- 日経テレコンを無料で利用できる
- IPOが完全平等抽選
- ポイント投資の対象商品が豊富
日経テレコンはスマートフォンで読める手軽さも魅力です。スマートフォンアプリiSPEED(アイスピード)からログインし、「メニュー」→「日経テレコン」と操作すれば起動できます。

IPOを完全平等抽選で配分する点も楽天証券のメリットです。
楽天証券は原則としてIPOの100%を抽選で配分します。預かり資産などで当選確率を調整することもありません。一方、SBI証券の平等抽選は全体の60%です。30%はIPOチャレンジポイントの使用量が多い順、10%はSBI証券が任意に割り当てます。
ポイント投資の種類が豊富な点も楽天証券のメリットです。
楽天証券では4つの商品(国内株式、米国株式、投資信託、バイナリーオプション)にポイント投資できます。国内株式は単元未満株も対象です。また投資信託はスポット購入と積み立ての双方に対応しています。
これだけ多くの商品にポイント投資できるのは、主要なネット証券でも楽天証券だけです。
 |
 |
 |
 |
 |
|
| 国内株式 | 〇 | 〇 | ― (※2) |
― | ― |
| 単元未満株 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ― |
| 米国株式 | 〇 (※1) |
― | ― | ― | |
| 投資信託 (スポット) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
| 投信積立 | 〇 | 〇 | ― | ― | 〇 |
| バイナリーオプション | 〇 | ― | ― | ― | ― |
| 公式サイト |
口座を 作る |
口座を 作る |
口座を 作る |
口座を 作る |
口座を 作る |
SBI証券と楽天証券のデメリットを比較

SBI証券と楽天証券には多くのメリットがある一方、デメリットもあります。共通のデメリットとしては、IPOの競争率が高いこと、メンテナンスが多いことが挙げられます。
SBI証券は国内株式と米国株式のアプリが別々である点、楽天証券は地方の単独上場企業に投資できない点などがデメリットです。
SBI証券と楽天証券に共通するデメリット
SBI証券と楽天証券に共通するデメリットとして以下が挙げられます。
- IPOの競争率が高い
- メンテナンスが多い
SBI証券と楽天証券はIPOの競争率が高く、当選確率は低くなります。
SBI証券と楽天証券の口座数は業界トップクラスです。多くの人が口座を開設していることから、IPOの応募も多いことが予想されます。そのため、SBI証券と楽天証券は多くのIPOを取り扱いますが当選する確率は高くないと考えられます。

複数の証券会社で口座を開設するとIPOの当選確率を上げることができます。
IPOの配分は複数の証券会社で行われることが一般的です。各証券会社で口座を持っていれば、同一銘柄へ複数回の応募が可能です。
応募を増やすほど当選確率は上昇します。当選を目指すなら、複数の証券会社で口座を開設しIPOに備えるのが良いでしょう。
若山卓也(ファイナンシャル・プランナー)
メンテナンスの頻度が高いことも、SBI証券と楽天証券に共通するデメリットです。
証券会社はシステムや機器の保守のためにメンテナンスを行っています。メンテナンス中はログインや取引が制限されることがあります。
SBI証券と楽天証券はメンテナンスの頻度が高いことで知られます。例えば定期メンテナンスは以下のようなスケジュールで行っています。これに加え、臨時メンテナンスも行われます。
| 予定日時 | |
| PCメインサイト (全てのサービス) |
毎日3:00~7:00頃 金曜16:00~20:00頃 日曜2:00~4:00頃 |
| スマートフォンサイト (全てのサービス) |
営業日7:30~7:30頃 日曜4:30~5:30頃 |
| SBI証券 株アプリ (全てのサービス) |
毎日6:20~6:30 日曜4:10~4:40 |
| 予定日時 | |
| 国内株式の注文不可 | 月~金7:30~7:40 月~金16:00~17:15 |
| 全商品の注文不可 (米国株式、先物・オプションを除く) |
火~土3:00~6:00 |
| ログイン不可 | 日曜2:30~3:30 |
SBI証券のデメリット
SBI証券のメリットには以下のようなものがあります。
- 国内株式と米国株式のアプリが別々
- クレカ積立のポイントが付与されないケースがある(2024年11月以降)
SBI証券は国内株式と米国株式を一つのアプリでできないデメリットがあります。
SBI証券の取引アプリは国内株式と米国株式で分かれています。国内株式は「SBI証券 株アプリ」で、米国株式は「SBI証券 米国株アプリ」で取引します。
楽天証券のiSPEEDのように、同一アプリで完結させることができません。
また、2024年11月以降、クレカ積立でポイントを受け取れない可能性があることもSBI証券のデメリットです。
SBI証券のクレカ積立は2024年11月買付分からポイント付与率が引き下げられます。三井住友カード(NL)と三井住友カード ゴールド(NL)は、年に10万円以上のカード利用がなければポイントは付与されません。一方、楽天証券のクレカ積立なら必ずポイントを受け取れます。
楽天証券のデメリット
楽天証券のデメリットは以下の通りです。
- 地方の単独上場企業に投資できない
- 投信保有ポイントの対象銘柄が少ない
楽天証券には「地方取引所(※)の銘柄を売買できない」というデメリットがあります。
※地方取引所:東京、大阪、名古屋以外の地域にある証券取引所
楽天証券の国内株式の取扱市場は東京証券取引所と名古屋証券取引所です。福岡証券取引所と札幌証券取引所は取り扱っていません。したがって、地方取引所だけに上場する銘柄の取引はできません。
主要なネット証券で地方取引所に対応していないのは楽天証券だけです。
投信保有ポイントの対象銘柄が少ないことも、楽天証券のデメリットです。
ネット証券の多くは投資信託の保有に対し毎月ポイントを付与しています。公社債投信(MRFやMMFなど)や上場投信(ETF、REITなど)といった一部の投資信託を除き、原則として全銘柄を対象とすることが主流です。
しかし楽天証券では対象銘柄を限定しています(投信残高ポイントプログラム)。対象銘柄の数は2024年5月23日現在で6本です。その他の投信信託を保有しても、毎月のポイント付与はありません。
- 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド
- 楽天・S&P500インデックス・ファンド
- 楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド
- 楽天・日経225インデックス・ファンド
- 楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド
- 楽天・SOXインデックス・ファンド
※出典:楽天証券(2024年5月23日現在)
SBI証券・楽天証券の口コミ
実際に「SBI証券」「楽天証券」で口座開設をしている人の口コミを確認していきましょう。
SBI証券のいい口コミ
- 国内株の手数料がゼロなのがいい!
-
なんといっても国内株式の売買手数料がゼロになる点が大きなメリットです。インターネットコースで電子交付サービス申込していれば、現物取引だけでなく信用取引、S株(単元未満株)も売買手数料がかかりません。
手数料を考えずに取引できるので、できるだけ手数料を安く抑えたいと考えている自分にピッタリでした。30代・男性
- 取扱銘柄数が多く、自分に合った商品を見つけられる
-
投資信託の取扱銘柄数が多いことがメリットに感じました。たくさんあるなかから、自分の好みに応じて選ぶことができたのでよかったです。
投資信託パワーサーチでは「つみたて投資枠対象銘柄」「成長投資枠対象銘柄」など新NISAの対象銘柄が分かりやすい点も魅力。信託報酬や信託財産留保額などもソートできるので銘柄探しに重宝しています。30代・女性
- ネットで簡単!PTSもできる
-
PTSがあるので、朝(8時20分~)や夕方(16時30分)でも取引できることは重宝します。ネット証券のなかには、PTSがないところもあるので日中あまり取引できない自分としては大きなメリットです。
40代・男性
SBI証券のよくない口コミ
- システムの不具合が多い
-
サイトのメンテナンスをしていることが多く、利用しようと思ったら、システムの不具合で利用できなかったことが何度かありました。
またカスタマーサポートに電話がつながりづらいところもデメリットです。NISAに関する電話問い合わせは土日もやっていることはよいのですが、待ち時間が長くて最終的には断念してしまいました。40代・女性
- IPOにまったく当選しない
-
IPOのブックビルディング時に大金がある人のほうが有利になる一面がある点はデメリットに感じます。投資資金が少額しか用意できない初心者の場合、IPOに応募してもなかなか当たりません。
20代・男性
- ページが見づらい
-
欠点の極めて少ない証券会社ですが、強いて言えばサイトのインターフェイスが見づらいです。私の場合、登録してから使い始めるまでかなり時間がかかりました。
投資初心者にとっては、情報量が多すぎてわかりにくいレイアウトだと思います。「間違ったところをタップしたらどうしよう?」と恐怖心さえ覚えました。もう少し感覚的に使えるUIに改善してほしいです。50代・女性
楽天証券のいい口コミ
- アプリが圧倒的見やすい
-
SBI証券と並び、二大ネット証券として名を馳せる楽天証券。私が楽天証券の最大の強みと考えているのは、そのアプリの見やすさと使いやすさです。
SBI証券のアプリはごちゃごちゃとしていて見にくく、操作も難しい一方、楽天証券は取引初心者でも簡単に操作可能なシステムが魅力。また、投資する中で貯まる楽天ポイントの汎用性もメリットです。20代・男性
- メインで使うべき証券会社だと思う
-
楽天証券なら、金融商品の数も多く、取引手数料も無料になっているので株を購入する際などに手数料をほぼ気にしなくていいところがおすすめです。
貴金属や債券、信用取引など商品にも幅広さがあり、メイン口座として使っていくにはすごくいい証券口座だと言えます。 楽天ポイントも投資に運用できるので、その点もいいです。30代・男性
- ポイントが貯まる
-
楽天グループのサービスなので、毎月の楽天カードでの積立金額に応じて楽天ポイントが付与される点がいいところです。さらにただポイントが貯まるだけでなく、そのポイントを新NISAの積み立てにも活用できるところが楽天証券の最大の魅力といえます。
私は、旧NISAを楽天証券で口座開設をしていたので新NISAのサービス開始時は非常に簡単な手続きで終えられました。30代・女性
楽天証券のよくない口コミ
- 担当者がいるわけではない
-
ネット証券会社なので、担当職員が親切丁寧に投資の仕方を教えてくれる、ということはありません。
またポイントでも投資ができ、手軽に投資ができるのはいいですが、気軽すぎて自分の資産のキャパシティを超えて投資しないように気を付けることが大切かと思います。50代・男性
- 電話がつながりにくい
-
取引に関する疑問点の問い合わせをしようと思っても、電話が一向につながらず、最終的に問い合わせを断念してしまったことがありました。
人気の証券会社で、問い合わせも多いのだと思いますが、もう少し電話の繋がりやすさを改善してもらえたらいいな、と思います。40代・女性
- 制度がコロコロ変わる
-
投資信託を購入する際に、買い付け金額に応じた楽天ポイントがもらえますが、この付与ルールが改悪されたことは気に入りませんでした。
楽天の財務状態が良くないからだと思いますが、それ以外にもポイント付与のルールが変わることが多いので、情報が得られなかったり損をしてしまったりする可能性もあるため、注意が必要と思いました。20代・男性
出典:fuelle編集部がクラウドワークスで調査
Q&A
取引手数料の安さもSBI証券の魅力です。国内株式や投資信託の取引手数料は原則として無料です。米ドルの為替手数料も実質無料化されています。NISA口座なら米国株式や海外ETFの取引手数料もかかりません。
金融収益に次ぐ第二の収益がトレーディング損益です。2024年3月期では営業収益の28%を占めています。トレーディング損益は債券の販売やFXなどの収益から構成されます。
何らかの事故で分別管理がなされていなかったとしても、原則として投資者保護基金から1人1,000万円まで補償を受けられます。
IPO投資をしたい人には、SBI証券は特に向くと考えられます。SBI証券はIPOの取扱実績で業界トップクラスです。当選を目指すなら欠かせない証券会社といえるでしょう。
楽天証券は条件を満たすと楽天市場のポイント還元率が0.5%~1.0%上乗せされます。楽天カードや楽天キャッシュの積み立てで楽天ポイントを貯めることも可能です。楽天銀行の口座を持っているなら、楽天証券と連携すれば自動入出金や優遇金利のサービスが受けられます。
ただしSBI証券はクレカ積立のポイント付与率を2024年11月買付分から引き下げます。カード券種によっては、年間カード利用額が10万円未満だとポイント付与がありません。楽天証券のクレカ積立なら、カードの利用額にかかわらずポイントを受け取れます。
クレカ積立以外にカードを利用する予定がない場合、楽天証券を選ぶようおすすめします。

証券外務員一種、AFP、プライベートバンキング・コーディネーター資格保有。
Twitter:@FP38346079
証券外務員一種、AFP、プライベートバンキング・コーディネーター資格保有。
Twitter:@FP38346079
【こちらの記事も読まれています】