「とりあえず貯金をしなくては」と思っている人は多いでしょう。でも具体的に毎月どのくらい貯金すればいいのかは悩みどころ。他の人がどれくらい貯めているのかも気になりますよね。そこで年代別貯金額や、年収別の貯金額の目安を調べました。
また「固定費の見直し方」や、「おすすめの貯蓄方法」「お金を“増やす”方法」についても紹介します。あわせて参考にしてみてください。
貯蓄額、目安は手取りの1割?みんなはいくら貯めている?

よく耳にするのが、「手取りの10%を目安に貯金しよう」というフレーズです。
でも収入は人によって違いますし、家族と同居しているかどうかによって生活費は変わります。そのため「10%」と聞いてもピンとこないかもしれません。
実際に周りのみんながどのくらい貯金しているのか、統計調査を見ていきましょう。金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(2020年)」から、
・二人以上世帯の貯蓄割合
・単身世帯の貯蓄割合
を紹介します。
※金融資産保有額、年間手取り収入は中央値をご紹介しています。二人以上世帯の年代は世帯主の年齢で区分しています。
また各年代の「おすすめの貯金額」もあわせて紹介するので参考にしてみてください。
※貯金額は各家庭の事情でも変わってきます。また著者の主観も加わった金額のため、あくまで目安として確認してください。
20代の貯金額

| 二人以上世帯 | 単身世帯 | |
|---|---|---|
| 年間手取り収入(税引き後) | 400万円 | 200万円 |
| 金融資産保有額 | 235万円 | 81万円 |
| 年間収入(臨時収入含む)からの貯蓄割合 | 13% | 18% |
| おすすめしたい毎月の貯金額 | 3.3~6.6万円 | 1.6~3.2万円 |
独身の人も多いと思われる20代。今回の表では、金融資産を保有している人・世帯をご紹介していますが、調査結果では「金融資産がない」という単身世帯は43.2%、二人以上世帯は16.0%もありました。
「若く収入が少ないから貯蓄は難しい」と思われるかもしれません。しかしまだ家族にお金がかかることが少ない時期だからこそ、今のうちに収入の中からいくらかでも貯蓄をするクセを付けておくことをおすすめします。
二人以上世帯で扶養する家族が配偶者や乳幼児期の子どものみという人は、手取り収入の10~20%程度を貯めることを目標としましょう。
実家で親と同居している人であれば家賃や水道光熱費がかかりませんので、表の金額に2~3万円ほどプラスしてはいかがでしょうか。
\貯金にはつみたてNISAがおすすめ/
2021年6月時点
| 会社名 |  |
 |
 |
 |
 |
| 商品数 | 174本 | 177本 | 170本 | 151本 | 157本 |
| 売買手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 最低投資金額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
| ポイント還元 | Tポイント | 楽天スーパー ポイント 資産形成ポイント |
松井証券ポイント | マネックスポイント | 毎月ポイント |
| 積立コース | 毎月 毎週 毎日 |
毎月 毎日 |
毎月 | 毎月 | 毎月 |
| ココがおすすめ | 豊富な 商品ラインナップ |
楽天ポイント が貯まる |
マネックスポイントが貯まる | サポートが手厚い | 現物株式の取引手数料が最大5%割引 |
| 申し込む 公式サイトへ |
申し込む 公式サイトへ |
申し込む 公式サイトへ |
申し込む 公式サイトへ |
申し込む 公式サイトへ |
30代の貯金額

| 二人以上世帯 | 単身世帯 | |
|---|---|---|
| 年間手取り収入(税引き後) | 500万円 | 300万円 |
| 金融資産保有額 | 423万円 | 206万円 |
| 年間収入(臨時収入含む)からの貯蓄割合 | 13% | 16% |
| おすすめしたい毎月の貯金額 | 4.5万円 | 5万円 |
子育て中の人も多い30代。「お金を貯めるのはなかなか難しい」と感じる人も多いのではないでしょうか。
子どもが成長するにつれて教育費など必要なお金は増えていきます。「児童手当だけでも貯蓄に回す」など、工夫しながら貯蓄を続けてください。
※児童手当は子どもの年齢や所得により、5,000~1万5,000円と受取額が異なります。
二人以上世帯の人は家族にお金のかかる世代でもあります。無理せず毎月の手取り収入の10%程度の貯金を続けましょう。単身世帯の人は20%程度の貯金が理想です。
「毎月の手取り収入が少ない」という人であれば、ボーナスにはなるべく手を付けずにそのまま貯めることも検討してください。
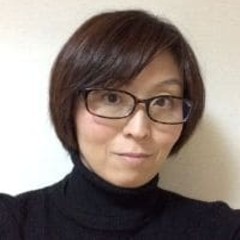
独身の人は、貯蓄を増やすのに最適な年代です。調査結果を見ても、20代に比べ金融資産保有額が大きく増えているのが特徴です。
余裕があれば、つみたてNISAやiDeCoなど積立型の投資へのチャレンジも検討してみましょう。
田尻宏子(ファイナンシャルプランナー)
40代の貯金額

| 二人以上世帯 | 単身世帯 | |
|---|---|---|
| 年間手取り収入(税引き後) | 520万円 | 250万円 |
| 金融資産保有額 | 686万円 | 400万円 |
| 年間収入(臨時収入含む)からの貯蓄割合 | 11% | 13% |
| おすすめしたい毎月の貯金額 | 2.1~4.2万円 | 4.1万円 |
40代の二人以上世帯では、子どもが成長し教育費がかかる年代になっているところも多いのではないでしょうか。
調査でも「貯蓄していない」と回答している世帯の割合が17.3%もありました。今はお金がかかる時期と考え、50代以降に貯蓄に力を入れることを考えてもいいかもしれません。
もし少しでも余裕があるのならば、積み立てでお金を貯めることも検討してください。
二人以上世帯は子どもの教育費にお金がかかる世代ですが、貯金する習慣は継続することをおすすめします。無理しない範囲で毎月の手取り収入の5~10%は貯めていきましょう。
単身世帯は老後の生活資金も視野に入れ始め、毎月の手取り収入の20%程度の貯金を続けましょう。
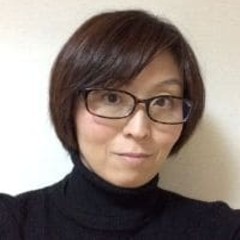
なお単身世帯は、老後のことを考え貯蓄をがんばりたい年代です。積み立ての預貯金や投資などでお金を作っていきましょう。興味があれば株式投資なども考えてみてはいかがでしょうか。
田尻宏子(ファイナンシャルプランナー)
50代の貯金額

| 二人以上世帯 | 単身世帯 | |
|---|---|---|
| 年間手取り収入(税引き後) | 600万円 | 220万円 |
| 金融資産保有額 | 1,000万円 | 622万円 |
| 年間収入(臨時収入含む)からの貯蓄割合 | 10% | 12% |
| おすすめしたい毎月の貯金額 | 10万円 | 3.6万円 |
50代は、定年に向けてお金を貯めていきたい年代です。
ただ勤務先によっては一定の年齢になると役職を解かれる「役職定年」がある可能性もあります。役職定年で収入が下がることもありますので、勤務先の規定をよく確認しましょう。
収入が減る場合、二人以上世帯・単身世帯ともに生活費に無駄がないか見直すことも必要です。
二人以上世帯の人は子どもの教育費負担がなくなったら手取り収入の20%程度を、単身世帯も同様に20%の貯金は続けましょう。
60代の貯金額

| 二人以上世帯 | 単身世帯 | |
|---|---|---|
| 年間手取り収入(税引き後) | 400万円 | 200万円 |
| 金融資産保有額 | 1,465万円 | 860万円 |
| 年間収入(臨時収入含む)からの貯蓄割合 | 8% | 8% |
| おすすめしたい毎月の貯金額 | 3.2万円 | 1.6万円 |
定年を迎えて収入が減ったり、なくなったりする人も多い年代です。収入がない場合は、公的年金支払い開始まで今の貯蓄でどのように生活するかを考えましょう。
もしくは、再就職やアルバイト・パートで収入を得ることも検討してください。
既に定年を迎えている人は貯金を増やすことが難しいかもしれません。お金を増やすことよりもなるべく減らさずに生活することに重点を置いてください。
もし定年を迎えていないのであれば、年収の10%程度の貯金をおすすめします。退職金制度がある企業に勤めている場合は、退職金がいくらほど入るかの確認も忘れないようにしましょう。
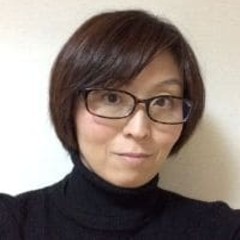
勤務先に「定年度再雇用制度がない」「再就職するつもりがない」という人は30~40代のうちから、つみたてNISAやiDeCoで積立投資を始めるなど対策を立てておきましょう。
田尻宏子(ファイナンシャルプランナー)
私はどう貯金したらいいの?最適な方法を確認
年代のおおよその収入額や貯蓄額をつかめたでしょうか。
しかし実際は、独身なのか結婚しているのか、子どもがいるのかいないのか、持ち家か賃貸か……など、それぞれの事情によって毎月貯金に回せる金額は異なります。
そこでここではどのくらいの額を毎月貯金に回したらいいのか、もしくはどうやって貯金したらいいのかをパターン別に目安として紹介します。
独身の場合
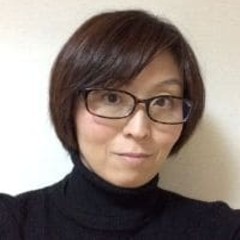
独身の方は家族がいる方に比べて、お金を自由に使える傾向があります。ただ、今後生活がどのように変わるか分かりません。そのため、なるべく貯蓄を積み重ねておくとよいでしょう。
田尻宏子(ファイナンシャルプランナー)
なお総務省「2020年家計調査」によると、単身世帯の住居費の平均は約2万1,000円、水道光熱費の平均は約1万1,000円です。
家族と同居している方であれば、この分のお金はかかりませんので、少なくとも毎月3万2,000円ほどは貯めることができるでしょう。
一人暮らしをしている人は、住居費や水道光熱費がどうしてもかかってしまいます。携帯電話料金など、見直しができる固定費があれば、削減して貯蓄に回しましょう。
貯蓄の方法は積み立てがおすすめです。次の方法を検討してください。

これらの中でも、勤務先が給与を天引きし積み立ててくれる「財形貯蓄」が特におすすめです。
夫婦2人暮らしの場合
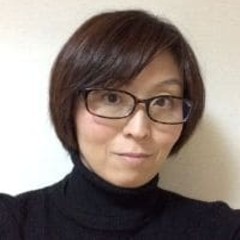
結婚し、夫婦2人暮らしの場合、次の点について考える方が多いのではないでしょうか。
・子どものこと
・家のこと
・老後のこと
独身の頃に比べて、考えなければならないことが増えますね。貯蓄についても様々な視点で進める必要があります。
田尻宏子(ファイナンシャルプランナー)
将来的に子どもを予定している場合は、今のうちから学費のための保険「学資保険」を調べておくとよいでしょう。
子どもの高校、大学進学タイミングで数十万~数百万のまとまったお金を受け取ることができます。学資保険の特徴は、以下の通りです。
・子どもが0歳(商品によっては出産前)から加入可能
・契約期間中、契約者(親)に万が一のことがあったら、その後の保険料は免除
また家の購入を検討する方もいるでしょう。家の購入資金を貯めるのには、貯蓄残高550万円まで利子に税金がかからない「財形住宅貯蓄」が有利です。勤務先に取り扱いがあるかを確認してください。
老後のお金についても少しずつ考え始める時期です。積立預金はもちろんですが、つみたてNISAやiDeCoといった投資を検討してみてください。
夫婦に子ども2人、4人家族の場合
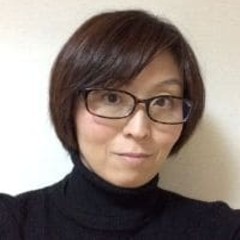
子どもが2人いるので教育費にお金がかかる可能性があります。貯蓄は続けていきたいところですが、難しい場合は勤務先の財形貯蓄だけでも続けるようにしましょう。
田尻宏子(ファイナンシャルプランナー)
多少余裕がある場合は、老後のお金作りにも着手してください。「ねんきん定期便」などで老後にもらえるお金の確認をしたうえで、前述のつみたてNISAやiDeCoでの資産形成を始めましょう。
子どもが学校を卒業し独立する時期に差し掛かったら、生活のダウンサイジングも考えてください。例えば次のような内容を見直しましょう。
・車を手放す
・無駄遣いをしない
定年後に備えて再雇用、再就職についても家族で話し合っておくことも大切です。
次からは、具体的な貯蓄の方法などを紹介していきます。
2021年6月時点
| 会社名 |  |
 |
 |
 |
 |
| 商品数 | 174本 | 177本 | 170本 | 151本 | 157本 |
| 売買手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 最低投資金額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
| ポイント還元 | Tポイント | 楽天スーパー ポイント 資産形成ポイント |
松井証券ポイント | マネックスポイント | 毎月ポイント |
| 積立コース | 毎月 毎週 毎日 |
毎月 毎日 |
毎月 | 毎月 | 毎月 |
| ココがおすすめ | 豊富な 商品ラインナップ |
楽天ポイント が貯まる |
マネックスポイントが貯まる | サポートが手厚い | 現物株式の取引手数料が最大5%割引 |
| 申し込む 公式サイトへ |
申し込む 公式サイトへ |
申し込む 公式サイトへ |
申し込む 公式サイトへ |
申し込む 公式サイトへ |
貯蓄額は平均値より中央値で読み解こう!各世代のリアルな貯蓄額はいくら?
貯金額UPのために毎月の「固定費」を見直そう

毎月の支出は、「固定費」と「変動費」に分けられます。「固定費」を減らすことができれば、その分を毎月貯蓄に回せるので効果が高くなります。
「固定費」とは、スマホ代などの通信費や光熱費、保険料、家賃、習い事代など毎月固定で発生する費用です。
とはいえ、家賃などはすぐに削減できるものではありません。しかし意外に見直しやすい「固定費」もあります。
例えば次のようなものなら取り組みやすいのではないでしょうか。
・定期購入のサプリメントや使い捨てコンタクトレンズなどの利用を見直す
・月会費を支払っているジムは本当に必要か検討する
・固定電話やネット通信費、水道光熱費の基本料金部分を見直す
・生命保険や損害保険を見直す
・サブスクサービスの利用を見直す など
毎月出て行く固定費は、「本当にそれが必要?」「もっと安いものはないか」という視点で一度整理するといいでしょう。
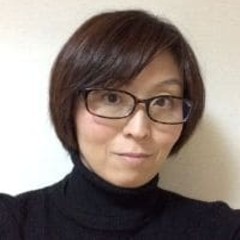
特にサブスクサービスなど趣味にかける費用は、複数のサービスを積み重ねていくと意外とかさむものです。毎月支払っている金額を確認して、断捨離してみてはいかがでしょうか。
田尻宏子(ファイナンシャルプランナー)
おすすめの貯蓄方法3つ

固定費を見直したらさっそく貯金をスタートしましょう!
ストレスなく貯金するためには「自動的に貯まる仕組みを作る」ことが大切です。毎月のお給料が入ってきたら、即座に貯金する分を取り分けましょう。
具体的には、どんな貯蓄方法がいいのでしょうか?おすすめの貯蓄方法を3つ紹介します。
銀行の積立定期預金
積立定期預金では、毎月決まった日に指定した普通預金口座から定期預金口座へ振替が行われます。
積立金額やボーナス月の増額なども自由に設定できて、満期日以降は自由に引き出せるので気軽にスタートできます。
2021年6月時点
| 会社名 |  |
 |
 |
 |
 |
| 商品数 | 174本 | 177本 | 170本 | 151本 | 157本 |
| 売買手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 最低投資金額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
| ポイント還元 | Tポイント | 楽天スーパー ポイント 資産形成ポイント |
松井証券ポイント | マネックスポイント | 毎月ポイント |
| 積立コース | 毎月 毎週 毎日 |
毎月 毎日 |
毎月 | 毎月 | 毎月 |
| ココがおすすめ | 豊富な 商品ラインナップ |
楽天ポイント が貯まる |
マネックスポイントが貯まる | サポートが手厚い | 現物株式の取引手数料が最大5%割引 |
| 申し込む 公式サイトへ |
申し込む 公式サイトへ |
申し込む 公式サイトへ |
申し込む 公式サイトへ |
申し込む 公式サイトへ |
財形貯蓄など会社の制度
財形貯蓄は、企業が導入する福利厚生制度の1つです。まずは、勤務先が導入しているかどうかを確認しましょう。
毎月の給与から天引きをして金融機関で貯蓄を行う仕組みで、貯蓄の目的によって3種類あります。目的や税制メリットを考えつつ、詳細を会社に確認してみてください。
解約などの手続きは勤務先を通して行う必要があるため、心理的にも「強制力」のある貯蓄方法と言えます。
デパートや旅行会社の積み立て
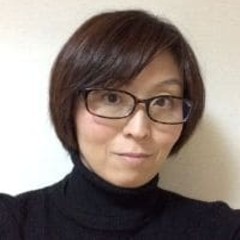
旅行が趣味の人、あるいはお気に入りのデパートがある人にはメリットのある方法です。旅行会社の定期積立では、積立期間・金額に応じて年利換算で1.75~3.0%程度になるケースもあります。
田尻宏子(ファイナンシャルプランナー)
積立先のサービスを必ず利用することが条件になりますが、例えば「お金を貯めて旅行する」と目標を決めればモチベーションも上がりますよね。
取り組んでみたい“お金を増やす”方法3つ

ある程度貯金が進んだら、取り組むべきは“お金を増やす”ことです。
お金を増やす方法にもいろいろありますが、できることからスタートしましょう。ここでは、3つの方法を紹介します。
つみたてNISA
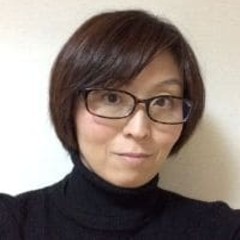
つみたてNISAは、少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。長期運用を前提に、積み立てでコツコツと資産形成したい人にはおすすめです。
田尻宏子(ファイナンシャルプランナー)
選定商品は、国が定めた低コスト、長期安定運用などの基準をすべて満たした一定の投資信託です。次のような5つのメリットがあります。
・投資による値上がり益や配当金・分配金にかかる税金が非課税
・年間最大40万円、合計800万円までが非課税投資枠
・途中でお金が必要になったときは、売却して引き出し可
・手数料が安い
出典: 金融庁『つみたてNISAの概要』
始めるハードルも低く、リスク分散にも効果的なつみたてNISA。おすすめのネット証券を紹介します。
2021年6月時点
| 会社名 |  |
 |
 |
 |
 |
| 商品数 | 174本 | 177本 | 170本 | 151本 | 157本 |
| 売買手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 最低投資金額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
| ポイント還元 | Tポイント | 楽天スーパー ポイント 資産形成ポイント |
松井証券ポイント | マネックスポイント | 毎月ポイント |
| 積立コース | 毎月 毎週 毎日 |
毎月 毎日 |
毎月 | 毎月 | 毎月 |
| ココがおすすめ | 豊富な 商品ラインナップ |
楽天ポイント が貯まる |
マネックスポイントが貯まる | サポートが手厚い | 現物株式の取引手数料が最大5%割引 |
| 申し込む 公式サイトへ |
申し込む 公式サイトへ |
申し込む 公式サイトへ |
申し込む 公式サイトへ |
申し込む 公式サイトへ |
iDeCo(イデコ)
iDeCo(イデコ)は、個人型確定拠出年金と言われる“自分で作る年金制度”です。
つみたてNISAと同じく長期運用で積立を行いますが、つみたてNISAと異なる点、そしてメリットは次の6点です。
・運用対象商品は投資信託以外に、定期預金と保険がある
・手数料の低い投資信託で運用
・原則60歳まで引き出しができない
・積み立てた掛け金にも税制優遇がある
・毎月5,000円から始めることができる
口座開設や維持に手数料がかかり、 途中で引き出せないものの、老後資金作りには最強の仕組みと言えるでしょう。
老後に向けた準備としてiDeCoを始めるのに、おすすめのネット証券をご紹介致します。
2021年5月時点
| 会社名 |  |
 |
 |
 |
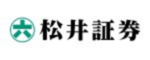 |
| 投資信託本数 | 36本 | 31本 | 26本 | 26本 | 39本 |
| 加入手数料 | ¥2,829 | ¥2,829 | ¥2,829 | ¥2,829 | ¥2,829 |
| 口座管理料 | ¥171 | ¥171 | ¥171 | ¥171 | ¥171 |
| サポート体制 | 平日・土曜 8:00~18:00 ※土曜は新規加入に関する 問い合わせのみ受付 |
平日10:00~19:00 土曜9:00~17:00 |
平日10:00~19:00 土曜9:00~17:00 |
平日9:00~20:00 土日9:00~17:00 |
平日8:30~17:00 |
| 特徴 | ・iDeCo加入者数No.1で10年の実績をもつネット証券最大手 ・iDeCo専用ロボアドバイザーによって好みに合った商品を選択できる |
・資産運用しやすい管理画面 ・無料セミナーなどの充実したサポート |
残高に応じてPontaポイントが貯まる(一部商品) | ロボアドバイザーによるiDeCo専用無料ポートフォリオ診断があり、簡単な質問に答えるだけで最適な資産運用が可能 | 「iDeCoシミュレーター」でiDeCoを利用した場合の節税額を簡単にチェックできる |
| 申し込む 公式サイトへ |
申し込む 公式サイトへ |
申し込む 公式サイトへ |
申し込む 公式サイトへ |
申し込む 公式サイトへ |
個人向け国債
国債は、国が発行する債券です。つまり、国に一定期間お金を投資して、定期的に利子を受け取り、満期になれば元本返済を受ける、という金融商品です。
次のような特徴があります。
・金融機関や証券会社で、1万円から購入可能
・発行後1年以上経てば途中で換金することも可
個人向け国債は「変動金利型10年満期」「固定金利型5年満期」「固定金利型3年満期」の3種類ありますが、おすすめは「変動金利型10年満期」です。唯一の変動金利タイプなので、今後金利が上がれば受取利子が増える可能性があるからです。
固定費を見直して貯まる仕組みを作る

各年代や生活スタイルによるおおよその貯蓄額の目安を紹介しました。自分の毎月の貯蓄額と見比べて、金額を調整してみてくださいね。
どの年代でも貯蓄を増やしたいときにまず行うべきことは、無駄の削減と固定費の見直しです。固定費は毎月必ず出て行く支出ですから、一度見直すと継続的に支出を削減できます。また、減らした固定費が自動的に貯まっていく仕組みを作りましょう。
給料が振り込まれたら、すぐに貯蓄分を取り分けます。勤務先に制度があるのならば、財形貯蓄を利用することをおすすめします。また貯めるだけでなく増やしたい場合は、つみたてNISAやiDeCo(イデコ )などの制度を利用するといいでしょう。自分に合った方法で貯金を始めてみてはいかがでしょうか。
「毎月の貯金額」の目安 Q&Aでおさらい
Q. 毎月いくら貯金するのがいい?
年代や収入、家族構成によって最適な金額は異なります。具体的にいくら貯金すればいいか、年代別に「目安の金額」を本編で紹介しているので参考にしてみてください。
Q. 独身におすすめの毎月の貯金方法は?
積み立てがおすすめです。「銀行の積立預金」「勤務先の財形貯蓄」などのほか、つみたてNISAやiDeCoなどで「積立投資」をするのもいいでしょう。
Q. 夫婦二人暮らしの場合、毎月どう貯蓄を進めるべき?
将来的に子どもを予定している場合は「学資保険」をチェックしておきましょう。また家の購入を検討している場合は、勤務先に「財形住宅貯蓄」がないかを確認してきましょう。さらに老後についても準備を開始しておくことをおすすめします。つみたてNISAやiDeCoでコツコツ積み立てを進めてください。
子どものこと、家のこと、老後のことなど、様々な視点で貯蓄についても考えておく必要があります。
Q. 子どもが二人いるのでお金がかかります。毎月の貯蓄は続けるべき?
できる範囲でいいので毎月の貯蓄は続けてください。多少余裕がある場合は老後のお金作りにも着手してください。「ねんきん定期便」などで老後にもらえるお金の確認をしたうえで、つみたてNISAやiDeCoでの資産形成を始めましょう。
【こちらの記事も読まれています】
>貯金専用口座はここがおすすめ!専門家が解説
>今からでも遅くない!老後資金をお得につくる「iDeCo」
>「つみたてNISA」の5つのメリット iDeCoとの違いは?
>ボーナスの手取り金額はこうやって計算しよう!