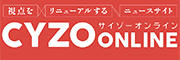ちなみに「被差別民」であることと、富裕であることは別問題で、矢野弾左衛門自身も「被差別民」でしたが、苗字帯刀を許され、吉原近隣の浅草新町(あさくさ・しんちょう)の屋敷に住み、その経済的実力は3000石の旗本級とか、一説によれば大名同然の暮らしを送っていました(ちなみに「矢野弾左衛門」とは代々世襲された名跡です)。
吉原は幕府が認めた色街で、町奉行の支配下にありましたから「被差別民」の客たちに大きく出られた一面もあったでしょう。しかし、吉原は弾左衛門の屋敷と距離的に近く、弾左衛門の配下たちが暮らす「穢多村」のご近所さんでもあったので、彼らの顔色をうかがい、法的には「被差別民」でなくなった後でさえ、歌舞伎関係者と遊女を遊ばせないルールを守り続けた可能性はあると思われます。
ドラマの時代より20年ほど前に刊行された『当世武野俗談』(宝暦6年・1756年)、幕末に刊行された『燕石十種』(文久3年・1863年成立)などにも、松葉屋の瀬川に惚れこんだ常磐津節の名人・文字太夫に対し、瀬川は会いはするけれど、「芸能関係の客は取らない」という吉原の掟に従って絶対に抱かれなかった……という逸話が紹介されています(ちなみに常磐津節から、派生したのが馬面太夫の富本節です)。ドラマの「鳥山瀬川」の話ではなさそうですが、興味深いですね。
さて、次回のドラマは「俄祭りの企画を巡り、大文字屋(伊藤淳史)と若木屋(本宮泰風)が争う。蔦重(横浜流星)は、祭りを描く本の執筆を平賀源内(安田顕)に依頼すると喜三二を勧められる…」という筋書きだそうです。「喜三二」とは、朋誠堂喜三二(ほうせいどう・きさんじ)などの筆名で知られる、久保田藩(現在の秋田県)の武士・平沢常富(ひらさわ・つねとみ/つねまさ・尾美としのりさん)のことですね。平沢は久保田藩の江戸留守居役で、江戸に定住し、幕府や他藩との折衝役をしていました。
前回のラストでも、鱗形屋(片岡愛之助さん)が『金々先生栄花夢』の作者・恋川春町(岡山天音さん)と打ち合わせをしていましたが、恋川の本名も倉橋格(くらはし・いたる)で、彼も小島藩(現在の静岡県にあった小藩)の武士でした。当時、多くの武士の仕事は昼過ぎには終わり、帰宅後は副業タイムでしたから、執筆時間も確保できていたのでしょう。副業は公認でしたが、彼らの執筆内容が(遊里など「悪所」を舞台にした)おもしろおかしい「黄表紙本」ですから、公にはできず、ペンネームで素性を隠す必要があったのです。