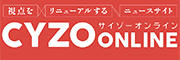そして西暦18世紀初頭までは、歌舞伎の演目の伴奏音楽として舞台で奏でられた浄瑠璃の演者たちの元締めも「長吏頭」こと矢野弾左衛門だったのですね。補足しておきますが、馬面太夫の富本節も浄瑠璃の一派です。
しかし、とある歌舞伎の公演が弾左衛門への「挨拶」なしに――つまり冥加金の類も出さずに始まったことから、弾左衛門の手下が舞台に上がって公演妨害したことでトラブルが表面化。これを機に弾左衛門の支配から脱したい歌舞伎関係者が、町奉行に訴え出る事件となりました。
大金を稼げる役者たちを支配下においておきたい弾左衛門でしたが、歌舞伎関係者には高位の武家や、大奥女中など有力者の隠れファンを持つ者も多く、旗色が悪かったようですね。宝永5年(1708年)、江戸歌舞伎の「宗家」とされる市川團十郎(二代目)が勝訴し、弾左衛門から独立できる喜びを『勝扇子(かちおうぎ)』という書物にまとめました。
この訴訟後は基本的に役者はもちろん、浄瑠璃の演者たちの身分も「賎民(=被差別民)」を脱して「良民(=一般人)」に昇格したはずなので、ドラマで描かれたように「当道座」の鳥山検校(市原隼人さん)といった有力者の支配下に入る必要が必ずしもあったのかな?とは思ったりはします。まぁ、鳥山検校の妻となった元・瀬川(小芝風花さん)こと現・瀬以と蔦重をつなげるためのドラマの演出でしょうかね……。
しかしその後も吉原では、彼ら歌舞伎関係者のことは、座敷に(彼らのパトロン客のアテンドとして)上げることは許しても、高級な遊女とねんごろになることは許さないというルールが守られ続けたそうです。
18世紀後半に出版され、吉原のさまざまな風習についてまとめた『吉原大鑑』という書物でも、客は遊女と遊ぶ前に「かわら者御法度の客にて御座なくといふ文言」を紙に書いて提出させられたという下りが出てきます。
「かわら者御法度の客」というのは、当時の「被差別民」にあたる職業の客という意味で自分は違うと念書を出す必要があったという意味です。