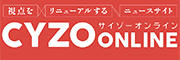江戸時代では芸能関係者でも能楽関係者には「士分」――正確には武士ではないけれど、それに準ずる高いステイタスが与えられていました。これはドラマの蔦重も指摘していたことです。
室町幕府の時代から足利将軍家が能楽・猿楽を好んだ結果、一般的に芸能関係は低く見られる中でも、「能楽」だけは武家の公式芸能として高く扱われるようになっていたのですね。
後に蔦重が役者絵を描かせた謎の絵師・東洲斎写楽も、能楽関係者の斎藤十郎兵衛だったといわれ、「士分」の能楽関係者が歌舞伎の役者絵「なんか」を描くことは大問題となりうる話だったのです。だから写楽は覆面絵師にならざるをえなかった……というわけですね。
ところが、能楽から派生した歌舞伎はもちろん、人形芝居関係者などのステイタスなども能楽関係者よりも低く見られていました。
そして穢多(えた)・非人(ひにん)といった「被差別民」たちを束ねる、自称「長吏頭(ちょうりがしら)」、幕府などからは「穢多頭(えたがしら)」と呼ばれた矢野弾左衛門の支配下に置かれていたのです。
以前のドラマでは、一橋治済(生田斗真さん)が田沼意次(渡辺謙さん)と共に「当世流」と称して人形を操って見せた場面で、田安賢丸(寺田心さん)が大人顔負けの苦言を呈していたことを覚えている読者もいるでしょうが、あのシーンも実はこういう芸能内のヒエラルキーと関連していたわけですね。人形つかい「なんか」のマネをするなど、高位の武士にふさわしい行いではない!というのが賢丸の主張です。
なお、戦国時代において「長吏」とは、武士たちから命じられ、鎧など武具の原料となる革を用意する仕事の人々を指しました。武士からは保護された一方で、牛や馬の死体から皮革を剥ぎ取らねばならず、その作業過程の血なまぐささなどによって、一般社会からは忌避されたのです。
仕事が昼過ぎに終わる武士の副業
こういう皮革産業従事者や、処刑人など一般人が嫌がる(とされた)仕事に携わってきた職能集団が、「被差別民」なのでした。江戸時代では「長吏」という言葉が、「穢多」「非人」をマイルドに表現する用語として使われたのです。