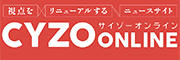高校野球とプロ野球を含めたマネジメントで大きく異なるのは、選手たちに2年半というリミットがある点だ。そのため、監督自身も幅広い経験をしながら、世代によって特性が変わったときに、うまく軌道修正できるよう、手札のバリエーションを豊かにすることで、世代はもちろんのこと、ルールや制度、環境などが変わっても対応できるだろう。
「外」からの視点も重要視することが鍵になる
現在の高校野球では、ビジネスパーソンから転身した人や、元プロ野球選手、外部コーチに指揮を任せる高校が増えている。従来のような高校野球漬けの監督なら、人生のほとんどをそれに捧げているため、高校野球における最適解に関しては、最短距離で見つけることができるだろう。
しかし、現在の高校野球はルールや制度の変化が激しく、優勝するためにはチームとして対応していかなければならない。そのため、主観的なものを念頭に入れながらも、俯瞰的な視点も必要になっていくのだ。例えば、極端な体育会系の環境の中だけにいると「こうでなくてはいけない」「ほかの選択肢はあり得ない」という思い込みが強くなり、健全な判断ができなくなることもある。
ただ、外部の視点から「それって普通じゃないよ」と言ってもらえるだけで、少し冷静な判断が下せる。
例えば、体育会系特有の過剰な“あいさつ”や“しごき”は一般的にはおかしいことだ。しかし、当事者はその判断ができない可能性は高い。そのため、外からの意見で、改善していくことが必要になってくるのだ。多様な視点を持つことで、自身の状態を適切に、健全に捉えられるようになる。そのため、一度、外に出ていた指導者は俯瞰的に野球というスポーツを見られるため、固定観念をなくした上で、チームづくりなどができる。
これは、元プロの監督や外部コーチにも言えることだ。外からの俯瞰的な視点がなければ、チームの課題点はもちろんのこと、自身の指導や采配の課題点は見つからない。自身が俯瞰的に把握しながらチームの課題を指摘し、改善できる人がリーダーとして上に立つことが今後重要になっていくだろう。
(文=ゴジキ)