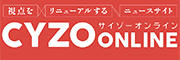小菅 これは東京に3つある弁護士会の中のひとつ、東京弁護士会の内部の組織である、非弁護士取締委員会が出したものです。
詳細な意図や経緯はわかりませんが、もしかしたら内部調査で、「非弁行為を行う退職代行サービスがここ1〜2年で急増している」という実態があがってきたのかもしれない。または、違法な業者が退職希望者から金を巻き上げ、法律に違反する行為をしているケースについて情報提供があったのかもしれません。
ーー弁護士会の声明は、その他の件も含めて、結構出るものなんですか?
小菅 弁護士会の声明の大半は、死刑判決が出たときや問題のある法律が制定されたときに会長が出すものです。東京弁護士会の非弁護士取締委員会に限ってみると声明を出すことは多くないようで、ウェブサイトの新着情報に出ているものは、「2024年11月22日 退職代行サービスと弁護士法違反」の1件だけです。
ただ、「非弁」ではなく、これに似た「非弁提携」だと、同様の声明はそれなりの数が出ているようです。2011年まで遡って、125件ヒットします。直近だと「国際ロマンス詐欺」や「非弁提携・アウトソーシング」などですね。
弁護士からしてみれば、非弁行為をする者は「けしからん」と思いますし、そのような企業や個人がいるならば、処罰を受けるべきです。ただ、非弁行為として実際に刑事告発まで至るケースは、各弁護士会の統計を見ても、そこまで多くないようです。
「退職代行サービス」は違法業者だらけなのか
ーーでは、今回問題視されている「非弁行為を行う業者」とは具体的にどんなことをしているのでしょうか?
小菅 まず「弁護士資格なしで法律事務を行うこと」は弁護士法違反(非弁行為) にあたります。例外的に、労働組合であれば、団体交渉として行える場合があります。そうした資格を有していない業者が、利用者の退職の意思を「伝える」だけなら”使者”という形で可能です。退職代行業者は、この使者を介して退職の意思を伝えることをもって”代行”と言っているようです。