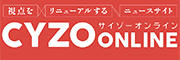使者ではなく、委任を受けた”代理人”弁護士の場合は、交渉もできます。例えば「未払い賃金の請求」「パワハラ慰謝料の請求」「有給消化の交渉」などです。一方で、”代行業者”は、依頼者の意思を伝えるという、使者としての役割以上のことはできません。退職代行業者が、法律事務を扱ってしまった場合は、「非弁」です。
「代理権とは」(裁判所Webサイトより)
courts.go.jp/otsu/vc-files/otsu/file/kouken25hosaninQandA-0404.pdf
さらに、退職代行業者が依頼料を受けとって、法律事務の処理をしてもらうために提携先の弁護士や労働組合に紹介することは、上記の東京弁護士会の声明によれば、非弁行為にあたり得るとされています。また提携先として、斡旋を受けた弁護士も非弁提携にあたる場合があります。
ーーそうなると、「退職代行サービス」と名乗っている企業で、弁護士と提携していると謳っていても、それが非弁提携にあたる場合があるわけですね。つまり、法律的にあいまいなところをついたビジネスだったものが、かなり話題になって目立ってきた。そこに、非弁護士取締委員会が待ったをかけた、ということなんですね。
小菅 企業側としては収益事業としてやってるわけですから、一般論として言えば、法律的にグレーなところを取り扱ったほうがお金になるわけですよね。退職代行サービスは、売上単価が比較的安く、大量集客が前提となっているビジネスモデルです。こうしたビジネスモデルはSNSとは相性がよいことから、ヒロイックな投稿がなされて盛り上がっている点から見ても、例えば利用者に「こういう風にSNSで投稿してください」といって、大衆の感情を煽ってPVを稼ぐような運用をすることも考えられます。
一方で、退職代行サービスを利用された企業側は、「どこそこの従業員が退職代行サービスを使ってきた、けしからん」などと呟くと、大炎上する可能性が高いので、黙っているしかない。そうすると、「退職代行を使ってブラック企業に一泡吹かせてやった」というわかりやすいストーリーが出来上がってしまう。さらにそれを第三者が、はやし立てて盛り上がりを見せるというメカニズムは、あるのかもしれません。