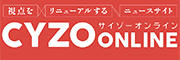小菅 おっしゃる通り、元々はブラック企業問題の中で注目されたもので、「辞めたいのに辞められない人を救う最後の手段」として位置づけられていたのではないでしょうか。実際に利用される方も「上司のパワハラがひどい」とか「暴力を振るわれる恐れを感じてしまう」という悩みを抱えていました。弊事務所が手掛けた限りですと、いわゆる大手企業できちんとした総務部や人事部があるようなところよりも、中小企業や個人事業主に雇われている方が多い印象です。
ここ数年でサービスがさらに広がった要因として考えられるのは、時代的な背景です。
ひとつは終身雇用が崩れ、雇用の流動性が非常に高くなったことです。かつては一度、新卒で就職したら簡単に会社を辞めるわけにもいかないという価値観がありましたが、非正規雇用や転職が増え、年々、会社を辞める人そのものが増えています。
またコロナ禍前後から「コスパ」に加え「タイパ(タイムパフォーマンス)」を重視する人が増えています。もし弁護士に一般的な交渉を依頼すると、最低でも10万〜20万円の弁護士費用がかかります。一方で、退職代行サービスであれば、弁護士が運営するものでも3万〜5万円程度で済む。加えて大半のサービスが、依頼すれば、即日または最大でも2週間程度で退職できると謳っています。この「安さ」「手軽さ」が、時代にマッチしているんじゃないでしょうか。
ーー「退職のハードルを下げた」という点ではメリットもありそうですね。
小菅 本当に必要な人にとっては有用なサービスです。一方で「本当に退職代行サービスを使うべきなのか?」というケースも増えていますが、これは上述のとおり、退職をめぐる価値観や倫理観そのものが変化してきているのかもしれません。
「東京弁護士会がついに動いた!?」――異例の声明、裏にある業界の本音
ーーそんな中、昨年末に東京弁護士会が「非弁行為を行う退職代行サービスを取り締まる」と声明を出しました。これはどういう意図があるのでしょうか?