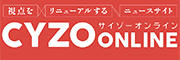近年は、記念館や歴史館といった施設を建てて集客するのがトレンドになっていますが、大河がきっかけで町が割れることも少なくありません。招致活動で官と民の足並みが揃わなかったり、招致が長引いて巨額の予算が市長選で争点になったり、招致に成功して浮かれてキャンペーンで大金を投じて問題になったり、トラブル例はいくらでもあります。偉人を巡って“生まれたのはウチの町”“育ったのはウチの村”と、取り合いをするケースもあります」(マネー誌記者)
民放元スタッフが見たNHKの“大河ドラマづくり”
それでも、1ケタ台がしのぎを削るこの低視聴率時代、視聴率2ケタをキープする大河の役割は大きい。元テレビ朝日プロデューサーの鎮目博道氏が、民放の立場からNHKの大河ドラマづくりに言及する。
「大前提としてNHKのドラマづくりは、その時その時に訴えたい社会的、政治的なメッセージが求められます。さらに朝ドラと大河の舞台は、全国まんべんなくやらなくてはいけないという難題がある。なぜなら、全国に受信料を払ってくださる視聴者がいるから、その人たちを大切にしないといけない。
地方も地方で、ご当地出身者が取り上げられると地方創生にもなるということで、陳情合戦です。その意味では、NHK大河は地方振興のために道路をつくる公共事業と同じ構図です」
ドラマ制作にあたり、鎮目氏は、「民放は“視聴者が求めているもの”を考えるけど、NHK、とりわけ大河は“自分たちの都合”によって内容が決まる」と、“ベクトルの違い”を指摘する。
「大河の路線が変わってきたように感じる背景にあるのは、第一に今のNHKの喫緊の課題として、若者を意識する必要があるということです。これから長い期間にわたって受信料を払ってもらうには、やはり若年層にアピールしないといけません。
そういう事情がある中で、そもそも今どきの若者は“定番”には飽きていて、刺激のある変化球がほしい生き物です。かつ経済成長が低迷している今の日本では、ギラギラとわかりやすく成功した人よりも、地味に努力して、密かに大きな案件に貢献していたようなタイプに光を当てたいというNHKの思惑もある。当時は負け組だったかもしれないけど、実はすごい人だった、というパターンですね。そうした人物像を考えた時、結局“誰?”という人選になるのは納得がいきます」