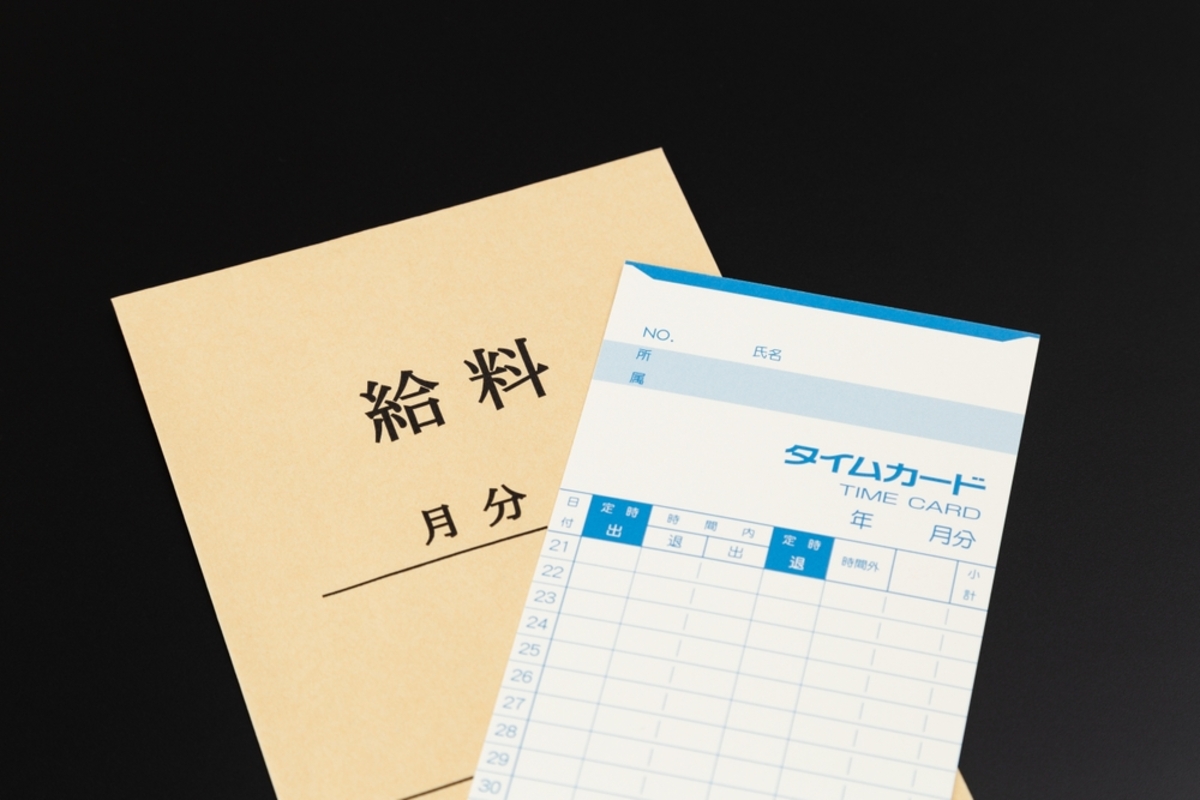
▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
出産後の女性の働き方は? 世帯収入にどれくらいの差が出る?
出産後の女性の働き方はさまざまで、以前の職場で就労継続したり、一旦離職してから再就職したり、再就職はせずに専業主婦になったりするケースが考えられます。それぞれのケースで、世帯収入にはどれくらいの差が出るのか気になる人もいるでしょう。
内閣府政策統括官(経済財政分析担当)が2024年6月5日に公表した「女性の出産後の働き方による世帯の生涯可処分所得の変化(試算)」では、女性の出産後の働き方別に、世帯の生涯可処分所得を試算しています。ケース別に比較すると、以下の通りです。
●正社員として就労後、出産してから正社員として就労継続:4億9200万円
●正社員として就労後、出産に伴い退職してからパートで再就職(年収100万円):3億5200万円
●正社員として就労後、出産に伴い退職してからパートで再就職(年収150万円):3億6400万円
●正社員として就労後、出産に伴い退職して再就職はしない:3億2500万円
正社員で就労継続するケースと、再就職しない場合を比較すると、税金・社会保険料支払い後の世帯の生涯可処分所得には1億6700万円の差が出るとのことです。出産に伴い退職してからパート勤務で再就職した場合でも、再就職しない場合より2700万円~3900万円多くなっています。
この試算では「夫婦は同年齢」「夫は22歳でフルタイム正社員として就労開始して65歳で退職」「男性は88歳、女性は93歳まで生きる」「29歳で第1子、32歳で第2子を出産」など、細かく共通の前提が設定されています。実際は各家庭で状況が異なるため一概にはいえませんが、一般論として、出産後の女性の働き方によって世帯の生涯可処分所得には大きな差が出ることが分かります。
