2020年に突入してから全世界で新型コロナウイルスの感染が猛威を振るっており、人類史上まれにみるパンデミックが現実問題となっています。一方、仮想現実である小説の世界においてもパンデミックをテーマにした作品は、たくさんあります。そこで今回は、アフターコロナを生き抜く知恵を考えるために読んでおきたい4冊の小説を紹介します。
1『ペスト』(新潮社)
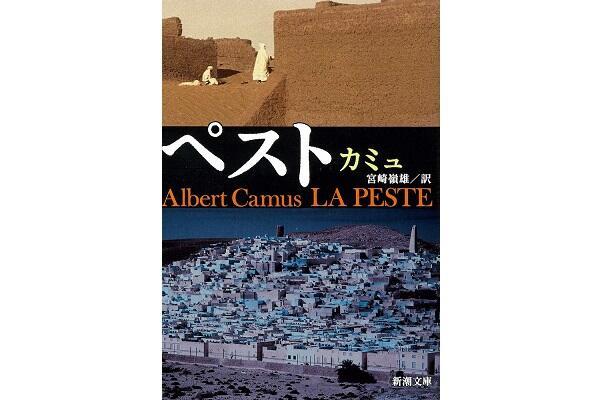
20世紀を代表するフランスの不条理文学の小説家として知られるアルベール・カミュが、1947年に出版した作品が『ペスト』です。ペストといえば、14世紀のヨーロッパをはじめ複数回パンデミックを引き起こしたことがある感染症で、感染者の皮膚が黒紫色になることから“黒死病”とも呼ばれています。
カミュが描いた『ペスト』は、そうした史実に基づいたドキュメンタリーではなく、あくまでもフィクションです。当時フランスの植民地であった北アフリカ・アルジェリアを舞台にペストが猛威を振るう中、市民たちがどう立ち向かったのかが描かれています。本書で描かれた「ペスト」は、感染症を意味するだけでなく、現実の戦争の経験とも重ね合わされているのが特徴です。
不条理文学の名の通り「人間がどうしようもない災厄といかにして戦うのか」をテーマとして見出すことができるでしょう。「ペスト」を「震災」や「コロナ禍」などさまざまな災厄に置き換えて本書を読み解くことができるはずです。
【基本情報】
著者:アルベール・カミュ
出版:新潮社
価格:文庫本825円(税込み)/電子書籍742円(税込み)
2『夏の災厄』(角川文庫)
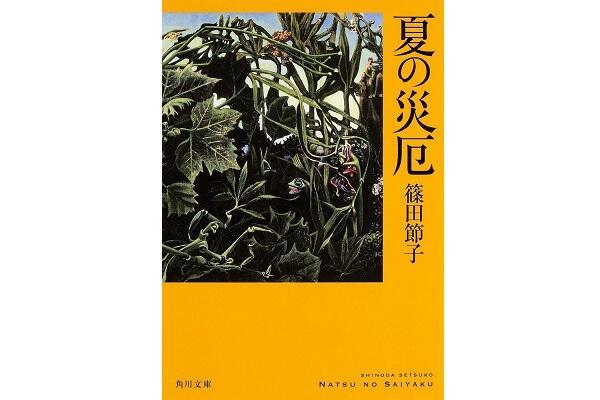
日本の小説家である篠田節子が1995年に発表した『夏の災厄』は、未知の感染症を題材にしたミステリー小説です。2015年に角川文庫より発売されていたものの、コロナ禍を受けて“予言書的な寓話”として注目を集め、2020年に重版されることになりました。『夏の災厄』は、郊外の町で新型日本脳炎らしきウイルスが登場します。
ウイルスにより住民がバタバタと倒れはじめ、保健所の職員や行政機関が感染拡大防止と原因究明にあたっていく少しホラーのような要素があるストーリーです。注目すべきはそのリアルさでしょう。「ウイルス自体の感染力や致死率」といった点以外にも、未知の感染症が発生したときの行政機関などの対応が克明に描かれているのです。
そのため、現実の日本政府や地方自治体が新型コロナウイルスに対処しようとする様子と、否が応にも重なります。本書を通じてウイルスへの対処方法について考えることで、「今何が必要なのか」が見えてくるのではないでしょうか。
【基本情報】
著者:篠田節子
出版:角川書店
価格:文庫本924円(税込み)/電子書籍832円(税込み)
3『モーム短篇選(下)』(サナトリウム)(岩波書店)
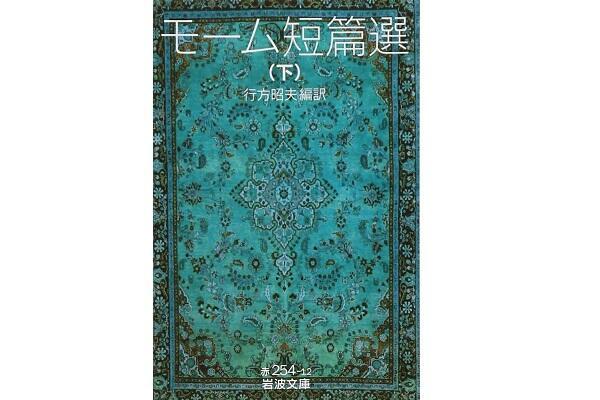
19~20世紀にかけて活躍したイギリスの小説家サマセット・モームによる短編の一つが「サナトリウム」です。まだ不治の病として知られていた結核患者が集う「サナトリウム」という療養所での人間関係が描かれています。実は著者のモーム自身、結核とは深い関係がある人物です。母親が肺結核で41歳という若さで死去しただけでなく、自身も14歳のときに肺結核に感染し療養生活を送っています。
さらに42歳のときにも再度肺結核に罹ってしまいサナトリウムに入院しているのです。しかし大事にはいたらず、モームは91年の長い生涯を送ることになりました。結核の実体験を持つ著者が執筆した「サナトリウム」からは、「感染することと生きること」「死と愛とは何か」といった普遍的なテーマを読み解くことができるでしょう。
【基本情報】
著者:サマセット・モーム
出版:岩波書店
価格:文庫本1,012円(税込み)












































