株式投資には証券会社の口座が不可欠です。しかしどの証券会社を選べばいいのか、迷う人も多いのではないでしょうか。
証券会社選びにはいくつかポイントがありますが、「手数料」はとても重要な要素の1つです。手数料が安い証券会社ほど有利に取引できるためです。
本記事では証券会社の「手数料」に着目し、手数料が安い証券会社ランキングTOP10をご紹介します。記事の後半では手数料以外の選び方についてもご紹介しますので、ぜひ証券会社選びの参考にしてください。
FPが選ぶ「ネット証券手数料ランキング」

なぜ証券会社選びで手数料が大切なのでしょうか。それはどの証券会社で取引しても株式の価値は全く同じなので、手数料が安いほど利益が大きくなるといえるからです。
そこで証券会社の「株式手数料ランキング」をまとめました。証券会社選びの参考にしてください。
| 取引金額ごとの株式手数料(税込) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | ||
| 1位 | SBI証券 | 無料 | 無料 | 無料 | 1,013円 | 1,013円 |
| 2位 | 楽天証券 | 無料 | 無料 | 無料 | 1,013円 | 1,013円 |
| 3位 | 岡三オンライン証券 | 無料 | 無料 | 無料 | 1,430円 | 1,650円 |
| 4位 | 松井証券 | 無料 | 無料 | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 |
| 5位 | むさし証券 (ネット取引) | 82円 | 192円 | 352円 | 484円 | 484円 |
| 6位 | DMM.com証券 | 88円 | 198円 | 374円 | 660円 | 660円 |
| 7位 | LINE証券 | 99円 | 275円 | 535円 | 1,013円 | 1,013円 |
| 8位 | GMOクリック証券 | 96円 | 265円 | 479円 | 917円 | 917円 |
| 9位 | auカブコム証券 | 99円 | 275円 | 1,089円 | 2,079円 | 3,069円 |
| 10位 | マネックス証券 | 110円 | 495円 | 550円 | 2,200円 | 2,750円 |
※株式手数料は、手数料が最も安くなる取引コースで計算しています。
それぞれの特徴を解説します。
1位:SBI証券
- 1日100万円の取引まで無料(アクティブプラン)
- 25歳以下は100万円超の取引でも実質無料
- 投資信託の販売手数料無料
SBI証券はネット証券トップシェア。「ネオ証券化(手数料ゼロ化)」を目標に、手数料の引き下げを断行してきました。
株式手数料には2コースがありますが、うち「アクティブプラン」なら1日100万円まで手数料無料で取引できます。また25歳以下なら取引金額にかかわらず手数料が全額キャッシュバックされるため、100万円以上の取引でも手数料負担がありません。
投資信託の販売手数料は全銘柄で無料です。手数料重視ならSBI証券が有力な選択肢といえるでしょう。
| 取引手数料(税込) | |
|---|---|
| スタンダードプラン | ~5万円:55円 ~10万円:99円 ~20万円:115円 ~50万円:275円 ~100万円:535円 ~150万円:640円 ~3,000万円:1,013円 3,000万円~:1,070円 |
| アクティブプラン | ~100万円:0円 ~200万円:1,278円 ※以降、100万円増加ごとに440円ずつ加算 |
2位:楽天証券
- SBI証券とほぼ同等の手数料体系
- 1日100万円の取引まで無料(いちにち定額コース)
- 投資信託の販売手数料無料
楽天証券も手数料が安いネット証券です。
1位のSBI証券とほぼ同等の手数料体系で、「いちにち定額プラン」なら1日100万円まで手数料無料で取引OK。投資信託の販売手数料が無料な点もSBI証券と同じです。
| 取引手数料(税込) | |
|---|---|
| 超割コース | ~5万円:55円 ~10万円:99円 ~20万円:115円 ~50万円:275円 ~100万円:535円 ~150万円:640円 ~3,000万円:1,013円 3,000万円~:1,070円 |
| いちにち定額コース | ~100万円:0円 ~200万円:2,200円 ~300万円:3,300円 ※以降、100万円増加ごとに1,100円ずつ加算 |

【100万円超の取引&25歳以下取引でSBI証券に劣る】
楽天証券の「いちにち定額コース」は1日100万円以下の取引まで手数料無料ですが、100万円を超えるとSBI証券の「アクティブプラン」より高くなってしまいます。
例)1日100~200万円の取引
・SBI:1,278円(アクティブプラン)
・楽天:2,200円(いちにち定額コース)
100万円を超えるなら事前に取引コースを変更すればいいですが、つい取引金額が超えてしまうこともあるでしょう。また25歳以下の手数料無料もありません。この2点がSBI証券との差になりました。
若山卓也(ファイナンシャルプランナー)
3位:岡三オンライン証券
- 1日100万円の取引まで無料(定額プラン)
- 25歳以下は100万円超でも手数料実質無料
- 投資信託の販売手数料無料
岡三オンライン証券も上位2社とほぼ同等の手数料体系です。1日100万円まで無料で取引でき、投資信託の販売手数料も無料です。25歳以下の手数料も無料化しています。
| 取引手数料(税込) | |
|---|---|
| ワンショット | ~10万円:108円 ~20万円:220円 ~50万円:385円 ~100万円:660円 ~150万円:1,100円 ~300万円:1,650円 ※以降100万円増加ごとに330円ずつ加算 ※手数料の上限:3,300円 |
| 定額プラン | ~100万円:0円 ~200万円:1,430円 ※以降、100万円増加ごとに550円ずつ加算 |

【取引ごとの手数料が若干高め】
1日の取引金額が100万円を超える場合、取引ごとに計算する手数料コースの方が一般に有利になります。岡三オンライン証券では「ワンショットコース」が該当しますが、上位2社より手数料が高めです。
このため、冒頭の手数料ランキング(手数料が最安になるよう計算)では3位となりました。
若山卓也(ファイナンシャルプランナー)
4位:松井証券
- 定額系コースのみ。1日50万円の取引まで無料
- 25歳以下は手数料無料
- 投資信託の販売手数料無料
松井証券の手数料は定額系コースしかありません。1日50万円までは無料ですが、50万円を超えると1,100円の手数料がかかり、その後は100万円ごとに1,100円ずつ増加します。手数料は最大11万円まで上昇するので、大きな金額で取引する人は注意が必要です。
なお25歳以下なら大きな取引でも手数料無料です。また投資信託も販売手数料無料で購入が可能です。
| 取引手数料(税込) | |
|---|---|
| ボックスレート | ~50万円:0円 ~100万円:1,100円 ~200万円:2,200円 ※以降、100万円増加ごとに1,100円ずつ加算 ※手数料の上限:11万円 |
5位:むさし証券(ネット取引)
- 手数料無料はなし(一部の投資信託は販売手数料無料)
- 「100万円超~600万円以下」の取引なら最安
むさし証券は手数料無料の設定はありませんが、取引ごとに手数料を計算するコース(トレジャースタンダード)の手数料が安い特徴があります。
100万円以下の取引は無料の上位3社に劣りますが、100万円超~600万円以下の取引なら10社で最も手数料が安いです。
比較的まとまったお金で取引する人におすすめの証券会社です。
| 取引手数料(税込) | |
|---|---|
| トレジャースタンダード | ~10万円:82円 ~20万円:104円 ~50万円:192円 ~100万円:352円 ~150万円:418円 ~300万円:484円 ~600万円:825円 ~900万円:1,452円 ~1,200万円:1,936円 ~1,500万円:2,420円 ~1,800万円:2,904円 ~2,100万円:3,388円 2,100万円~:3,872円 |
| トレジャーボックス | ~300万円:1,320円 ~600万円:2,640円 ~900万円:3,960円 ※以降、300万円増加ごとに1,320円ずつ加算 |
6位:DMM.com証券
- 手数料無料はなし
- 100万円超の取引は比較的安い。「600万円超」なら最安
- 25歳以下は手数料実質無料安
DMM.com証券は取引ごとに手数料を計算するコースしかありません。その手数料は比較的安く、600万円超の取引なら10社の中で最安となりました。ある程度まとまったお金で取引する人におすすめの証券会社です。
また25歳以下の場合は株式手数料が全額キャッシュバックされます。
| 取引手数料(税込) | |
|---|---|
| 1約定ごと | ~5万円:55円 ~10万円:88円 ~20万円:106円 ~50万円:198円 ~100万円:374円 ~150万円:440円 ~300万円:660円 300万円~:880円 |
7位:LINE証券
- 投資信託の販売手数料無料
LINE証券で株式を買う場合、手数料は購入金額により変動します。売買で考えると「むさし証券(ネット取引)」や「DMM.com証券」の方が概ね安くなるので注意しましょう。
LINE証券は売却を考えていない方にはおすすめです。例えば配当金や株主優待を目的に、株式を長期的に保有する方に向いているでしょう。
| 取引手数料(税込) | |
|---|---|
| 現物取引 |
~5万円:55円 ~10万円:99円 ~20万円:115円 ~50万円:275円 ~100万円:535円 ~150万円:640円 ~3,000万円:1,013円 3,000万円~:1,070円 |

【「いちかぶ」は必ずコストがかかる】
LINE証券は1株ずつ取引できる「いちかぶ」というサービスを行っています(通常は100株単位)。そちらは「スプレッド(取引コスト)」が必ずかかるので注意しましょう。
スプレッドは銘柄や時間帯ごとに異なり、その範囲は0.2~1.0%です。取引金額100万円なら2,000円~1万円に相当し、決して安いとはいえません。頻繁な取引には向かない点に留意しましょう。
若山卓也(ファイナンシャルプランナー)
8位:GMOクリック証券
- 2コースから選択
- 手数料無料はなし(一部の投資信託は販売手数料無料)
GMOクリック証券の株式手数料は2コースあります。取引ごとに計算する手数料コース(1約定ごとプラン)は比較的安く、100万円超の取引なら10社の中でも安めです。
| 取引手数料(税込) | |
|---|---|
| 1約定ごとプラン | ~10万円:96円 ~20万円:107円 ~50万円:265円 ~100万円:479円 ~150万円:580円 ~3,000万円:917円 3,000万円~:977円 |
| 1日定額プラン | ~20万円:234円 ~30万円:305円 ~50万円:438円 ~100万円:876円 ~200万円:1,283円 ~300万円:1,691円 ※以降、100万円増加ごとに295円を加算 |
9位:auカブコム証券
- 取引ごとの手数料のみ
- 一部のETFは無条件で手数料無料
- 投資信託の販売手数料無料
auカブコム証券の手数料コースは取引1回ごとに計算するタイプだけです。なおauカブコム証券が指定する「フリーETF」は、手数料無料で取引できます。
また投資信託の販売手数料はすべて無料です。
| 取引手数料(税込) | |
|---|---|
| 現物取引 | ~10万円:99円 ~20万円:115円 ~50万円:275円 50万円~:0.099%+99円 ※手数料の上限:4,059円 |
10位:マネックス証券
- 2コースから選択
- 50万円超取引はアプリが便利(取引毎手数料コース)
- 投資信託の販売手数料無料
マネックス証券の株式手数料は2コースあり、いずれも10社の中では比較的高めです。
「取引毎手数料コース」の場合、専用アプリ「マネックストレーダー株式スマートフォン」で取引した方がいいでしょう。取引金額50万円超の手数料が一律0.11%になります。
| 取引手数料(税込) | |
|---|---|
| 取引毎手数料コース | ~10万円:110円 ~20万円:198円 ~30万円:250円 ~40万円:385円 ~50万円:495円 ~100万円:(成行)1,100円 (指値)1,650円 100万円~:(成行)0.11% (指値)0.165% ※50万円超の場合、スマホアプリは一律0.11% |
| 一日定額手数料コース | ~100万円:550円 ~300万円:2,750円 ※以降、300万円ごとに2,750円ずつ加算 ※21回目からは2,475円、121回目からは1,815円 |
【少額投資を行いたい人】株式手数料を比較

証券会社選びに役立つよう、冒頭のランキング上位4社「SBI証券」「楽天証券」「岡三オンライン証券」「松井証券」をさらに比較してみましょう。4社の中からどれを選べばいいか参考になると思います。
まずは「少額投資を行いたい人」のため、100万円以下の取引手数料を比較しましょう。
| 50万円の取引 | 100万円の取引 | |
|---|---|---|
| SBI証券 (アクティブプラン) |
無料 | |
| 楽天証券 (いちにち定額コース) |
無料 | |
| 岡三オンライン証券 (定額プラン) |
無料 | |
| 松井証券 | 無料 | 1,100円 |
SBI証券・楽天証券・岡三オンライン証券の3社は、1日の株式の取引金額が100万円まで手数料がかかりません。少額取引を行う場合は上記3社のいずれかを選ぶといいでしょう。
ただし手数料無料で取引を行う際は取引コースに注意しましょう。上記3社は取引コースを定額系の手数料コースに変更しないと手数料が無料になりません。
【まとまった金額で取引したい人】株式手数料を比較

次に「ある程度まとまった金額で取引をしたい人」のため、100万円超取引の手数料をまとめます。
| 200万円の取引 | 300万円の取引 | |
|---|---|---|
| SBI証券 (スタンダードプラン) |
1,013円 | 1,013円 |
| 楽天証券 (超割コース) |
1,013円 | 1,013円 |
| 岡三オンライン証券 (ワンショット) |
1,650円 | 1,650円 |
| 松井証券 | 2,200円 | 3,300円 |
ランキング上位4社の中で100万円超の取引を行いたい場合、SBI証券か楽天証券を選ぶといいでしょう。
「ノーロード(販売手数料0円)投資信託」の取り扱い数を比較
投資信託も選択肢の1つです。販売手数料が無料の「ノーロード投資信託」の取り扱い数を比較してみましょう。
なお、ランキング上位4社はいずれも投資信託すべての販売手数料が無料です。
| ノーロード投資信託の取り扱い数 | |
|---|---|
| SBI証券 | 2,648本 |
| 楽天証券 | 2,692本 |
| 岡三オンライン証券 | 560本 |
| 松井証券 | 1,454本 |
ノーロード投資信託が最も多いのは楽天証券で、2位はSBI証券となりました。両者はどちらも2,600本を超えています。
他2社も少ないわけではありませんが、投資信託にも投資したい場合は楽天証券かSBI証券を選ぶといいでしょう。
証券会社の手数料 Q&A

証券会社の手数料について、初心者が抱きやすい疑問点と、その回答をご紹介します。
Q:手数料はいつ発生するの?
株式の場合、「買い」と「売り」双方で手数料がかかります。そのほかの手数料は基本的にありません。
投資信託の場合、「買い(販売手数料)」と「保有中(信託報酬)」の手数料がかかります。一部「売り」でコスト(信託財産留保額)がかかるものもありますが、多くはありません。
Q:手数料にはどんな種類があるの?
証券会社によっては、手数料ではなく「スプレッド」や「サービス利用料」といった名前の取引コストがかかります。これらは実質的に手数料と同じなので、どれくらいのコストになるか冷静に比較しましょう。
上述の手数料以外では「入出金手数料」や円と外貨を交換する「為替手数料」などがあります。口座そのものには手数料がかからないことが一般的です。
Q:海外株の手数料って?
海外株の手数料も国内株式と同じく、取引金額ごとに設定されています。
注意点は「為替手数料」もかかるという点です。例えばアメリカ株式を買う場合、米ドルを用意しないといけません。円を米ドルに交換する際にかかる手数料が為替手数料です。
円と外貨を交換するほど負担が重くなってしまいます。海外株式の取引を続けるなら、取引のたびに円に戻すのではなく、外貨のまま置いておくといいでしょう。
Q:手数料以外にかかる金額はある?
手数料以外で気を付けたいのは「税金」です。基本的に利益の20.315%が税金として売却金額から引かれます。
税金は証券会社の口座(特定口座)内で自動的に計算し、源泉徴収されます。したがって、確定申告は一般的に必要ありません。
手数料以外にも着目!証券会社選びのポイント

ここまで手数料に着目して証券会社を紹介してきました。しかし、実は手数料以外にも証券会社選びに大切なポイントはあります。
手数料以外の証券会社選びのポイントを確認しましょう。
つみたてNISAなどへの取り組みはどうか
投資にはさまざまな優遇制度が用意されており、それらを利用したほうがお得です。
優遇制度はすべての証券会社が一律でやっているわけではなく、取り組みに差があります。優遇制度を提供していない証券会社もありますが、より有利な運用をしたいなら、そのような証券会社は避けたいところです。
主な優遇制度には、「NISA」「つみたてNISA」「iDeCo」があります。これらへの取り組みがどうなっているか、事前に確認して証券会社を選択しましょう。
投資情報や投資ツールの豊富さはどうか
投資判断は各自で行うものですが、判断材料となる投資情報が豊富な証券会社を選びたいですよね。
証券会社は、それぞれ投資情報を提供しています。その質を比較するのは難しいですが、どのような投資情報や投資ツールが用意されているかは、各社のホームページで確認できます。
| 証券会社 | 無料の投資情報 |
|---|---|
| SBI証券 | ロイター社、フィスコ社など |
| 楽天証券 | 日経テレコンなど |
| 岡三オンライン証券 | 自社レーティング、レポートなど |
| 松井証券 | Quick社など |
| むさし証券 (ネット取引) |
市況ニュースなど |
| DMM.com証券 | 四季報など |
| LINE証券 DMM.com証券 |
自社コラムなど四季報など |
| GMOクリック証券 LINE証券 |
日経社など自社コラムなど |
| auカブコム証券 GMOクリック証券 |
自社の取引データ、 フィスコ社など日経社など |
| マネックス証券 auカブコム証券 |
バロンズ社、自社マーケット情報など 自社の取引データ、フィスコ社など |
| マネックス証券 | バロンズ社、 自社マーケット情報など |
証券会社は基本的に無料の投資情報が充実しています。中には有料の投資情報や投資ツールもありますが、無料のものでも基本的な情報は入手できるでしょう。
ネットか対面か
証券会社には大きく「ネット証券」と「対面式」があります。どちらを選べばいいのでしょうか。
基本的にはネット証券をおすすめします。対面式より手数料が安く、また取扱商品も充実している傾向があるためです。
ただしネット証券では情報の収集や投資判断をすべて自分で行わなければなりません。専門家に相談しながら投資を行いたい場合は対面式の方がいいでしょう。専任の担当者に相談しながら投資できます。
ネット証券と対面証券を比較してみよう
上述の通り、証券会社には「ネット証券」と「対面式」の2つのタイプがあります。どちらを選べばいいのか、選び方のヒントになるよういくつかの項目で比較してみます。
手数料の比較
まずは本記事の主題でもある手数料で比較してみましょう。ネット証券の方が安い傾向があるとお伝えしましたが、どれくらい異なるのでしょうか。
ネット証券は「SBI証券」と「楽天証券」、対面式証券は「野村證券」と「大和証券」を代表に、それぞれ比較してみましょう。
| 50万円の取引 | 100万円の取引 | ||
|---|---|---|---|
| ネット証券 | SBI証券 (アクティブプラン) |
無料 | |
| 楽天証券 (いちにち定額コース) |
無料 | ||
| 対面式証券 | 野村證券 (本店・支店) |
7,150円 | 1万2,188円 |
| 大和証券 (本店・支店) |
6,325円 | 1万2,650円 | |
ネット証券2社は100万円まで無料ですが、対面式証券2社は100万円で1.2万円超の手数料となりました。
本記事で紹介した10社と比較しても、対面式証券はかなり手数料が高いといえます。
売上高の比較
昔からある対面証券と比べると「ネット証券はなんとなく不安」と思う人もいるかもしれません。しかし、今やネット証券の規模はかなり大きくなっています。どれくらい大きいか分かれば不安を減らせるかもしれません。
まずは売上高(営業収益)の比較をしてみましょう。それぞれ親会社グループに属していますが、ここではその証券会社単体の売上高で比較しています。
| 売上高 | ||
|---|---|---|
| ネット証券 | SBI証券 (2021年3月期) |
1,603.56億円 |
| 楽天証券 (2020年12月期) |
723.06億円 | |
| 対面式証券 | 野村證券 (2020年3月期) |
5,897.04億円 |
| 大和証券 (2020年3月期) |
2,665.74億円 |
対面式証券2社の方が大きいですが、ネット証券の2社も大きな売上高実績を残しています。手数料の差を考えればかなり健闘しているといえるでしょう。
時価総額の比較
比較の4社はすべて上場会社グループの一員です。親会社の時価総額もチェックしてみましょう。「株価×発行株式数」で計算される数値で、一般に企業規模を測る指標とされます。
| 時価総額 | ||
|---|---|---|
| ネット証券 | SBIホールディングス (SBI証券) |
6,703億円 |
| 楽天グループ (楽天証券) |
2兆926億円 | |
| 対面式証券 | 野村ホールディングス (野村證券) |
1兆8,806億円 |
| 大和証券グループ本社 (大和証券) |
1兆444億円 |
最も大きな時価総額となったのは「楽天グループ」です。ただし、楽天グループは金融以外の業種も幅広く含むので単純な比較はできません。
金融グループとしては「野村ホールディングス」が上記で最大の時価総額といえるでしょう。次いで「大和証券グループ本社」が続き、「SBIホールディングス」は最下位となりました。
ただし「SBIホールディングス」も時価総額は7,000億円近くあり、十分大企業の一角といえます。ネット証券だからといって不安になる必要はないでしょう。
コストが低く便利な証券会社を選びましょう
証券会社選びでは、取引コストが安いネット証券を選択するのが基本ですが、投資の相談もしたいなら対面証券会社も選択肢に入ります。ご紹介したランキングや証券会社選びのポイントを参考にして、自分に合う証券会社を選ぶようにしましょう。
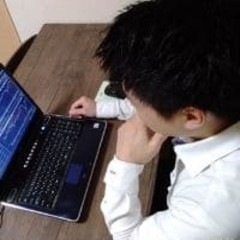
【こちらの記事もおすすめ】
>つみたてNISAにおすすめの口座ベスト3
>FP直伝!つみたてNISAの選び方3つのポイント
>つみたてNISAの商品はどう選ぶ?FP厳選おすすめ商品3つ
>つみたてNISAで投資初心者におすすめの証券会社はどこ?5社
>NISAとiDeCoはどちらがお得?特徴や違いをFPが解説