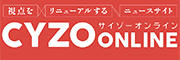──歴史エッセイスト・堀江宏樹が国民的番組・大河ドラマ『べらぼう』に登場した人物や事象をテーマに、ドラマと史実の交差点を探るべく独自に考察。
『べらぼう』第4回も楽しく拝見しました。その前回の内容については、次回の解説と合わせてお話していきましょう。
次回の内容は「蔦重(横浜流星)は鱗形屋(片岡愛之助)のもとで働き、のれん分けで本屋になる道を選択しようとしていた。そんな中、唐丸(渡邉斗翔)はある男にしつこく脅されていた…」とのことです。
前回は、蔦重が錦絵の版元(板元)として有名な西村屋与八(西村まさ彦さん)の協力を得て、奔走。吉原がプッシュする花魁に、呉服屋が売り出したい新作の着物を着せたファッションカタログのような錦絵集『雛形若菜初模様』を実現させ、平賀源内先生からいただいた「耕書堂」の堂号で見事に版元デビューを遂げた……と思いきや、制作発表の場に現れた鱗形屋の孫兵衛たちが蔦重に浴びせたのは「お前は正規の版元ではないから、本など出せない」という理屈の冷や水だったのでした。
それにしてもあれだけブチギレていた蔦重が、鱗形屋の食わせ物の旦那・孫兵衛にもう一度接近していく、とは面白くなりそう。
ということで、次回以降のドラマでも深堀りされていくとは思いますが、前回の補足も含め、お話していきましょう。
まずは版元問題から……。
「耕書堂」の印はなせ押されなくなったのか?
江戸時代の江戸で何かの本を出版したいとなれば、ドラマでも触れられたとおり、同業者たちの了解を得なくてはならないのです。『雛形若菜初模様』は実在の錦絵集で、安永4年(1775年)から天明元年(1781年)にかけて出版されたシリーズもので、いわば富裕層の女性に向けたお正月向けのファッションカタログでした。
ちなみに長屋に暮らしているような本当の庶民が着物を新調できたのは一生涯で数回あればいいほうだったといわれていますから、お正月の晴れ着を毎年新調できるのも良いとこのお嬢さま、奥さまに限った話です。